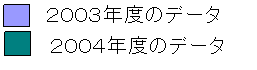
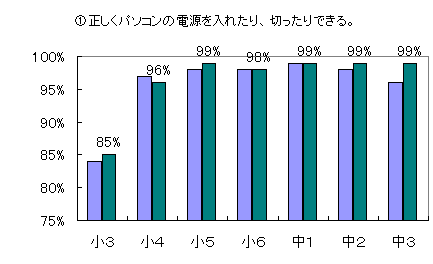
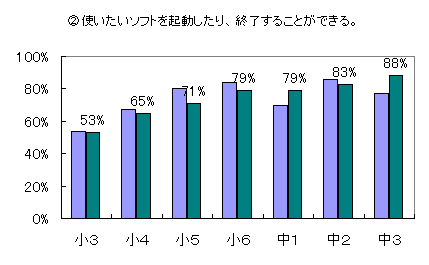
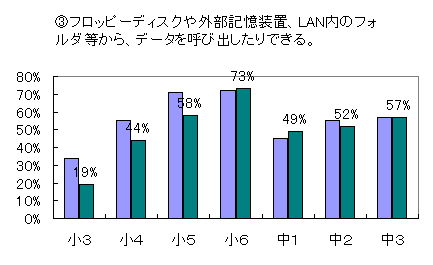
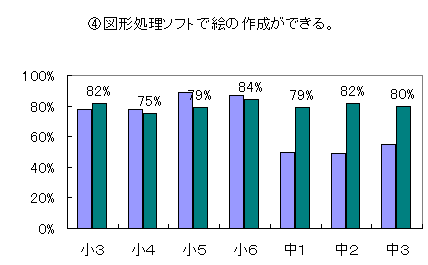
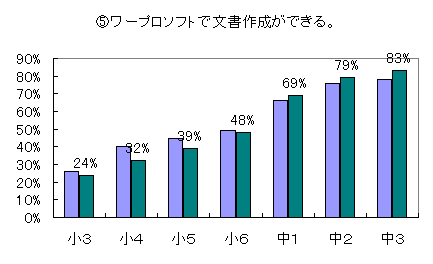
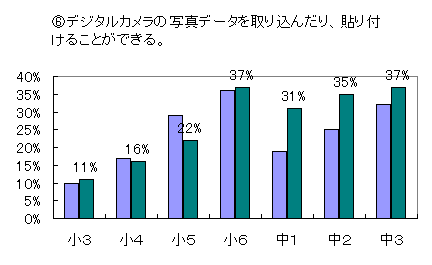
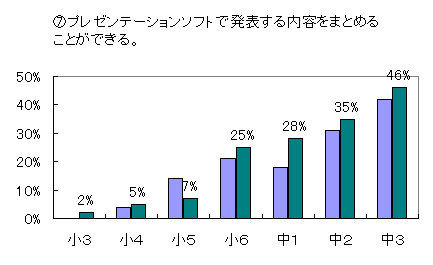
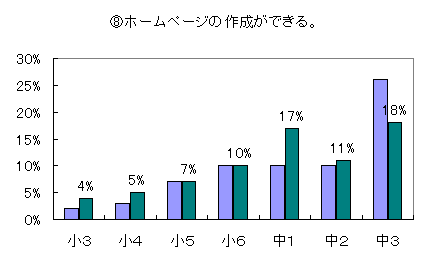
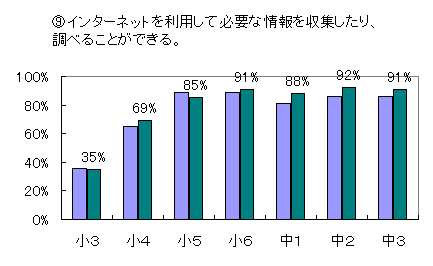
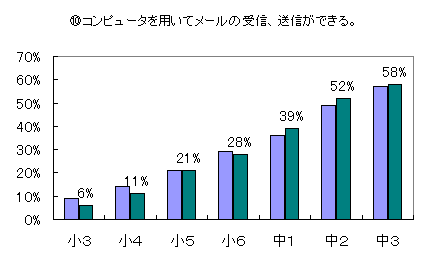
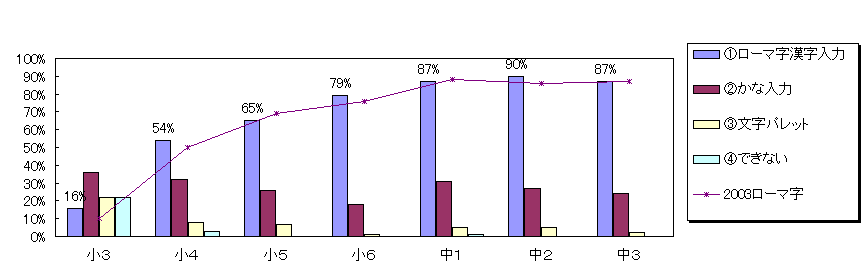
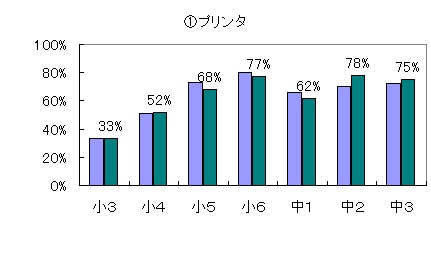
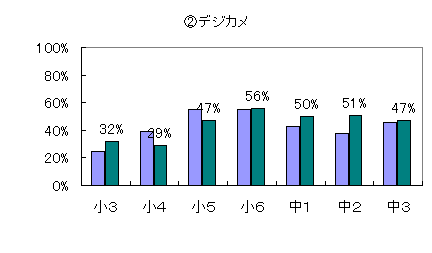
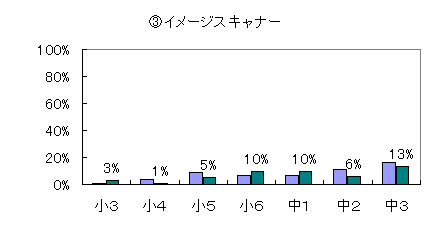
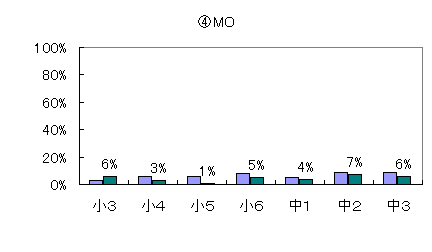
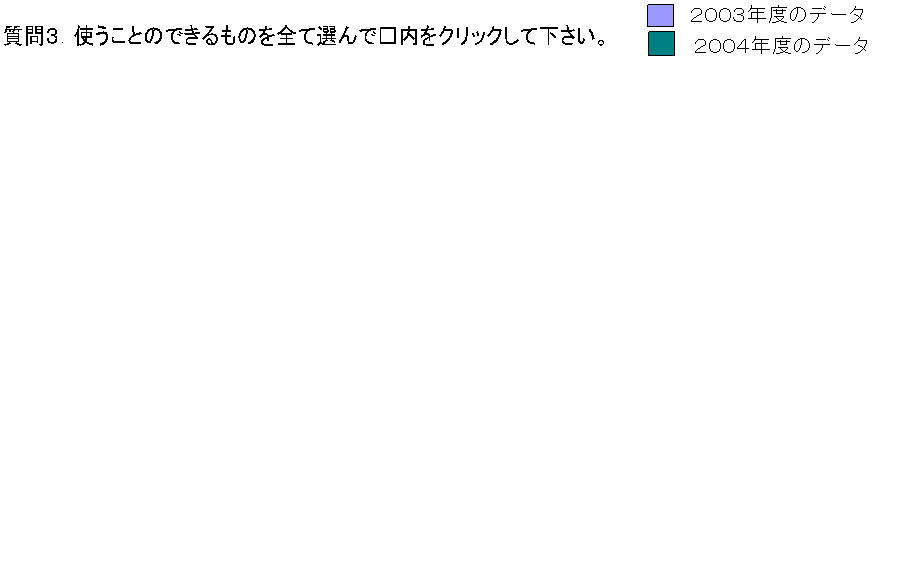
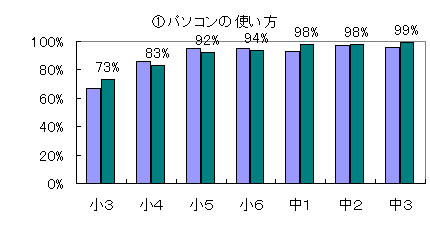 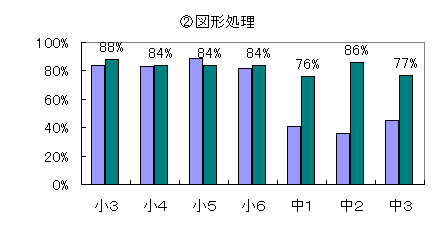 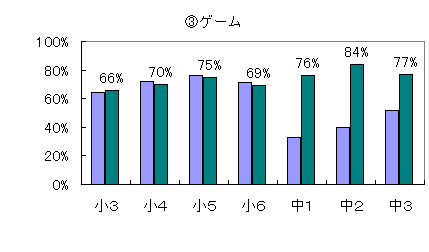 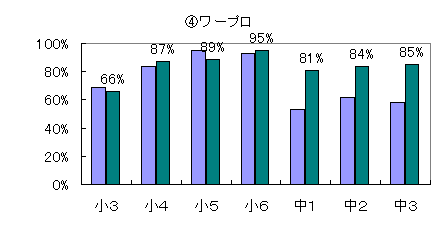 |
|||
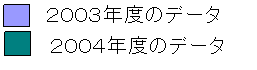 |
||
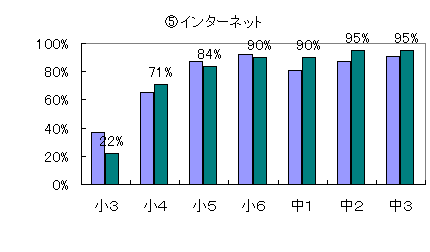
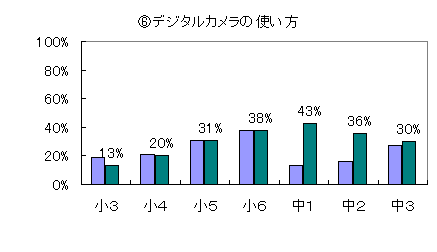
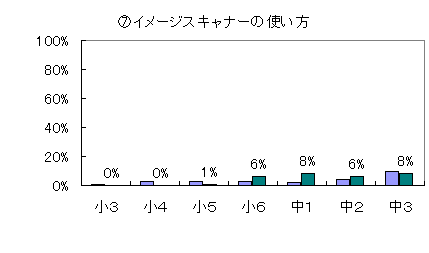
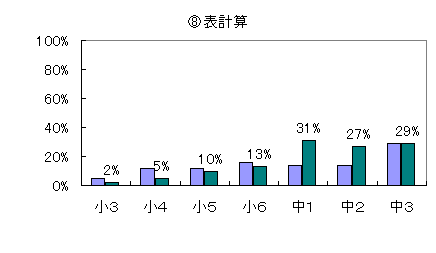
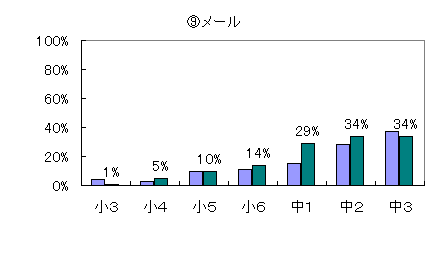
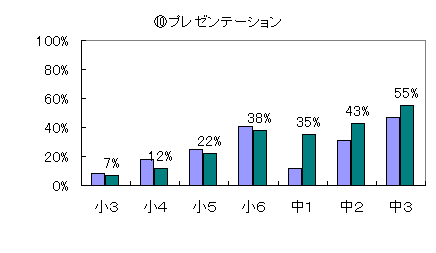
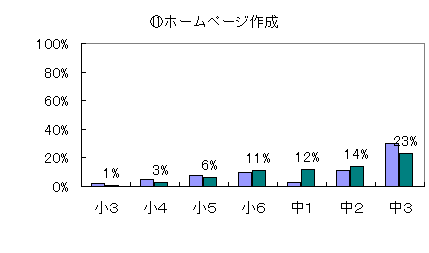
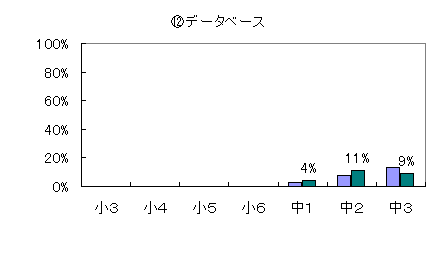
�@�قƂ�ǂ���������N�������悤���X���ɂ���A�������w�Z�ł��������ω��������Ȃ��悤�ł���B�������A���w�Z�������S�́u�������w�K�������e�v�́u���[�v���v��u�f�W�J�����g�����v�A�u�v���[���e�[�V�����v�ł��L�т������A���������A�����P�́u�ł��邱�Ɓv�ł��ʐ^�f�[�^���\���t����A�v���[���e�[�V�����\�t�g�ł̂܂Ƃ߁A�z�[���y�[�W����Ƃ������X�L���������ɂȂ������悤�ł���B�܂��A�C�́u�}�`�����\�t�g���G���쐬���ł���v�ł��g�p����\�t�g�E�F�A���u���G�����\�t�g�v�����Ƃ������߁A�}�`�����Ƃ����������C���[�W���L���Y��ł�����N�����l���啝���������Ă���B
�@�ǂ��������ق��E��������̃O���t�ɂȂ��Ă��邱�Ƃ���A�w�N���i�ނɈڂ�ăX�L����������������B�܂��A�����������������w�Z�����w�Z���������l���i���������A��������N�x�����������Ƃł͂Ȃ��A��N�������X���ł���B���w�Z�̂Ƃ��u�ł������Ɓv�����w���Łu�ł��Ȃ��Ȃ�v���������ɂ�����������������邱�Ƃ̂悤���v����̂������ۑ��Ƃ����l���Ă��������B
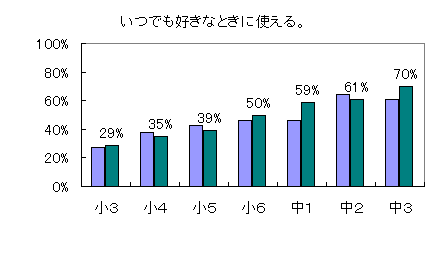
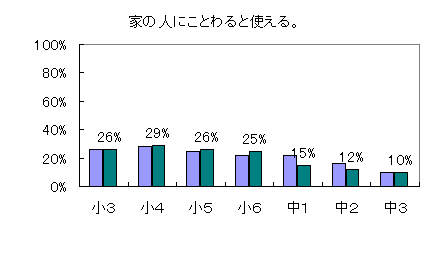
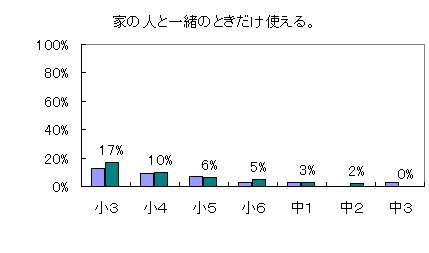
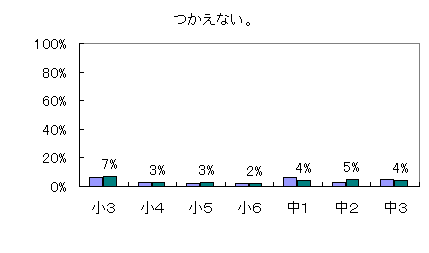
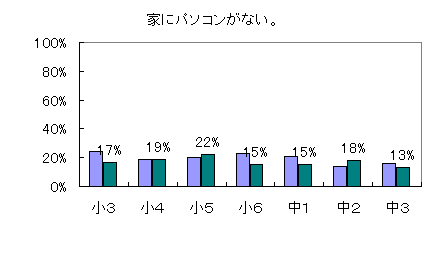
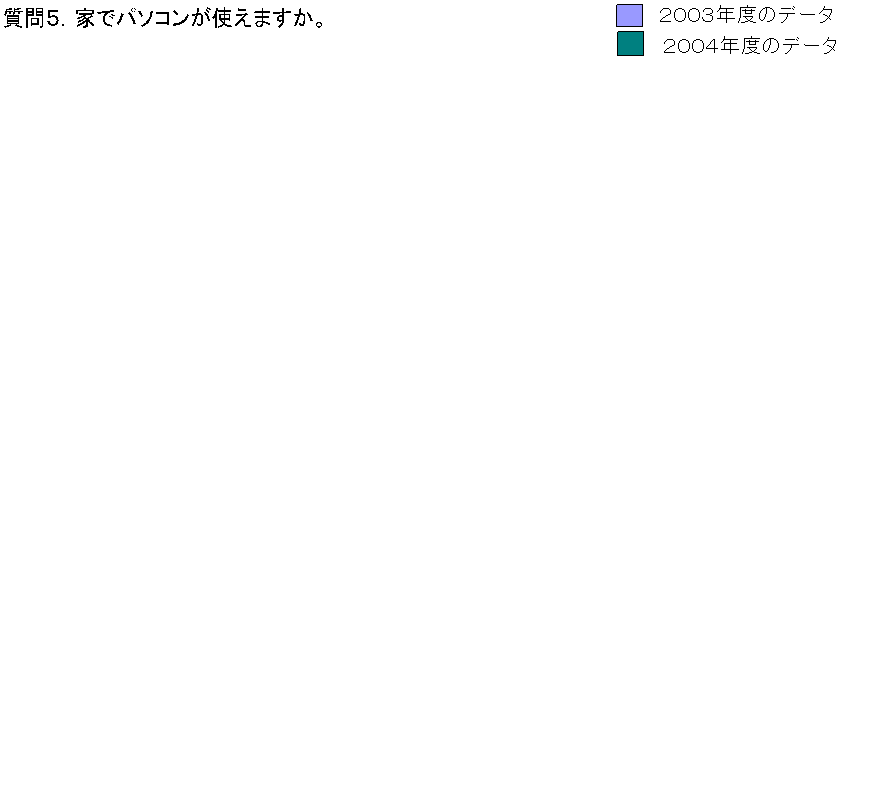
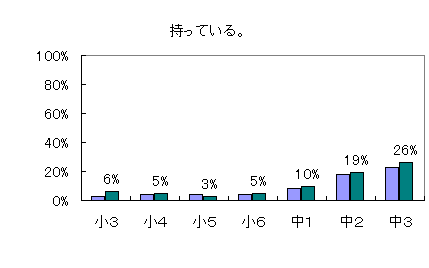
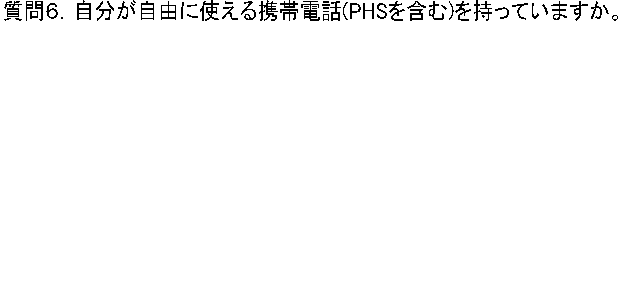
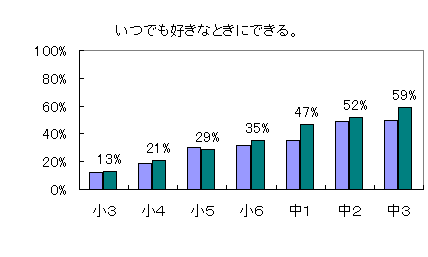
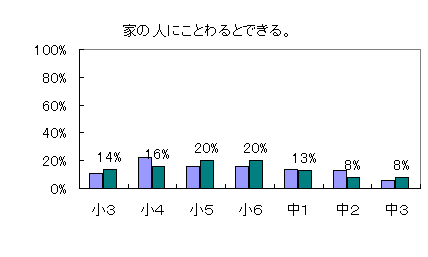
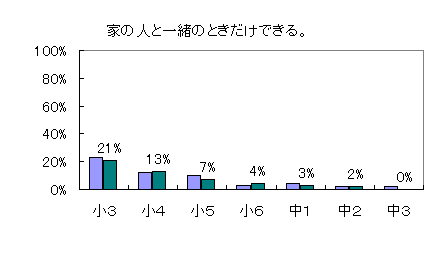 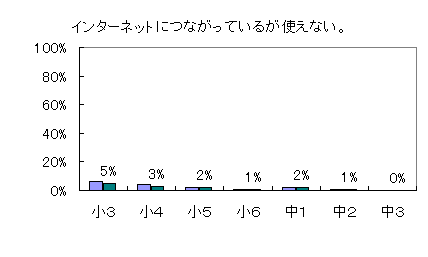 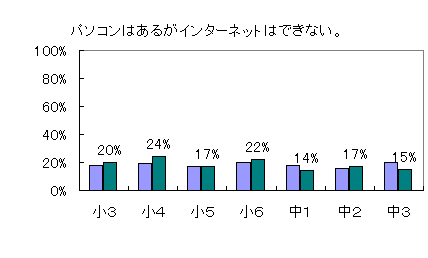 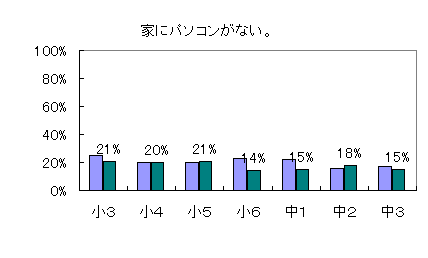 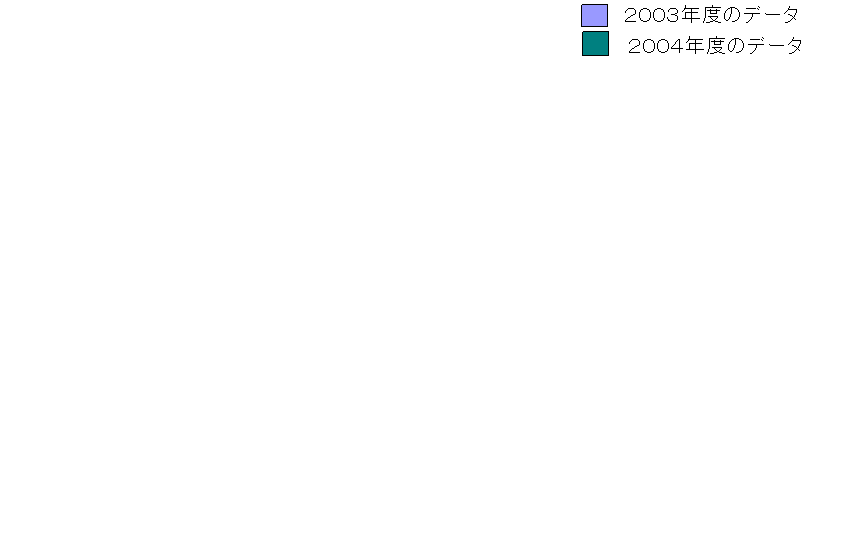 |
|||
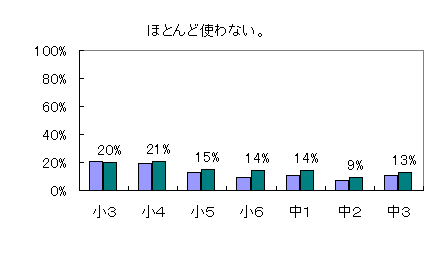
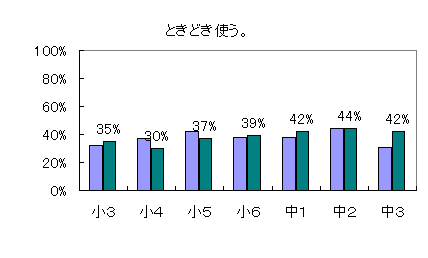
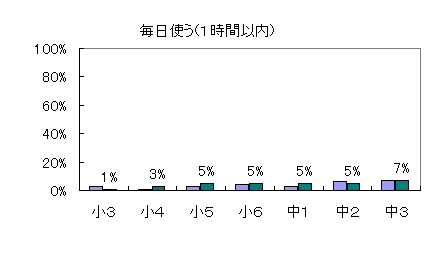
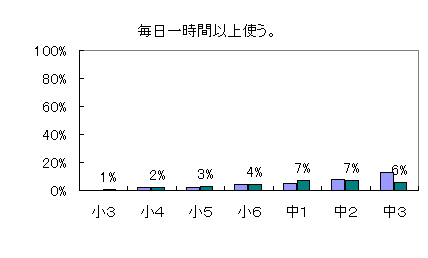
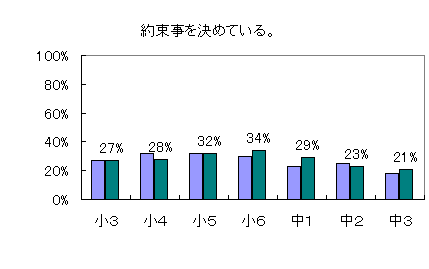
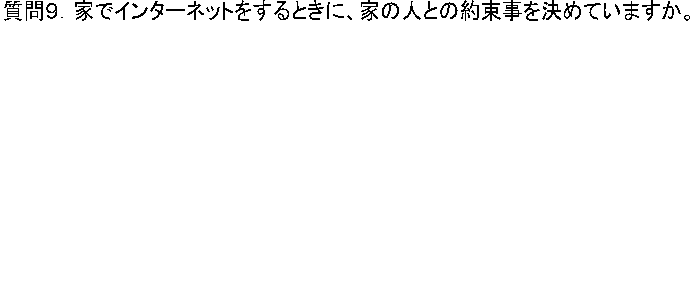
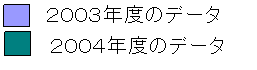 |
|||||
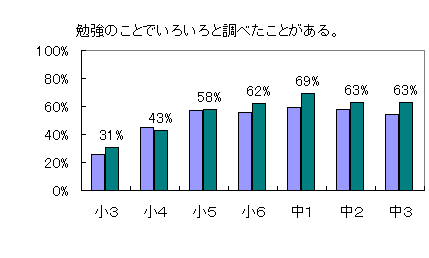 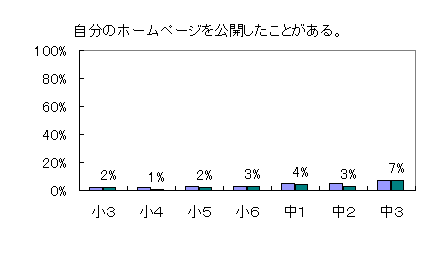 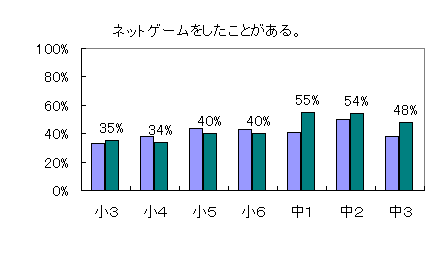 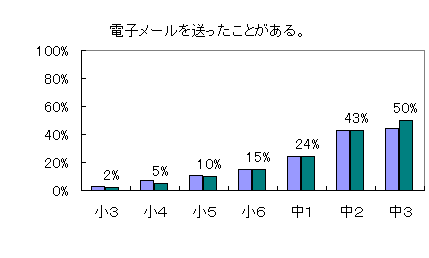 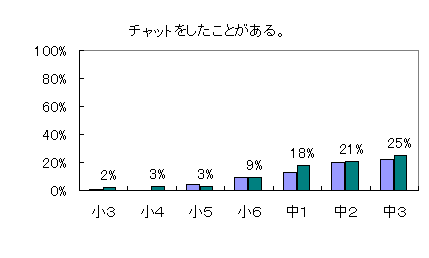 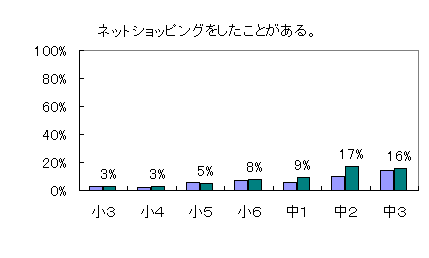 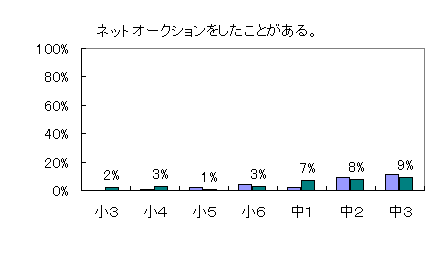 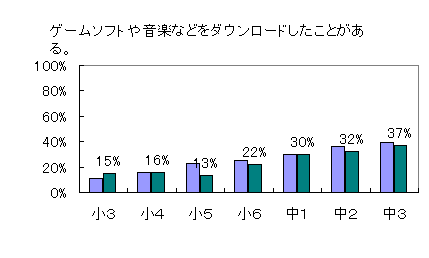 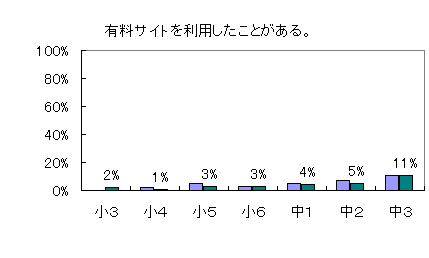 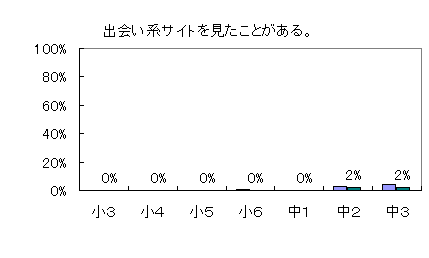 |
|||||
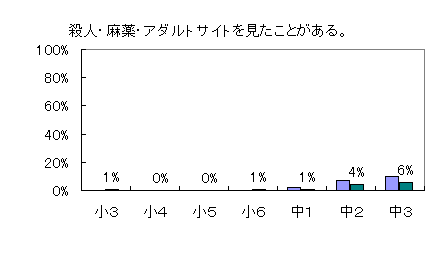
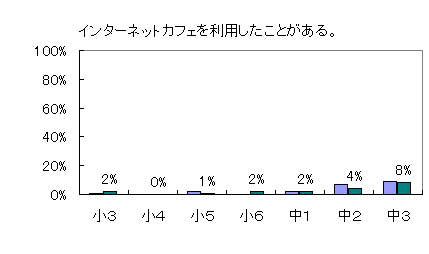
�@�R�`�s���������k���ƒ��ł̃p�\�R�����y���������P�S�N�x�̂V�Q�`�V�T���������N�x�͂W�O�`�W�T���ƂȂ�R�N�������P�O�����L�т��݂���B����������āA�����E���k���p�\�R�������p�����@���������A�C���^�[�l�b�g�������w�K�����p����邱�Ƃ�����g���ɂȂ����悤���B
�@�p�\�R�����y���������������A�{���ɂӂ��킵���Ȃ��T�C�g�ł�������������������������v���邪�A�o�����n�T�C�g���L���T�C�g�A�E�l�E�����E�A�_���g�T�C�g���{������N�x�������������ƂȂ��Ă��邱�Ƃ���A�ƒ��ł��L�Q�T�C�g�������Ȃ������i�߂��Ă��邱�Ƃ��킩��B�������A�����������O�ł͂Ȃ����Ƃ���A�L�Q�T�C�g���ɂ��Ă͂����̓I�������������Ă����Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ������ł����l����B�ǂ����ƒ��ł���y�������g�߂����@���������ł���悤�ɂ��Ă��������B
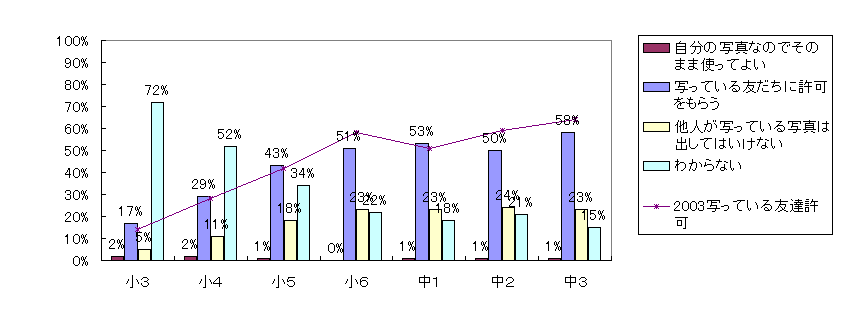
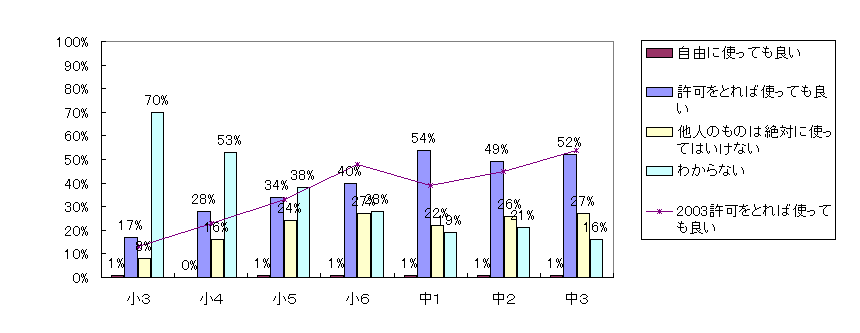
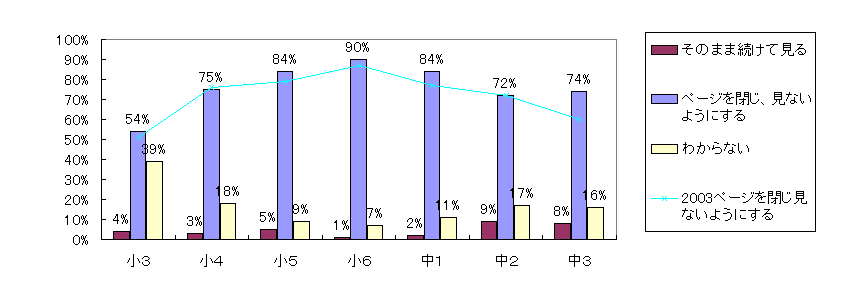
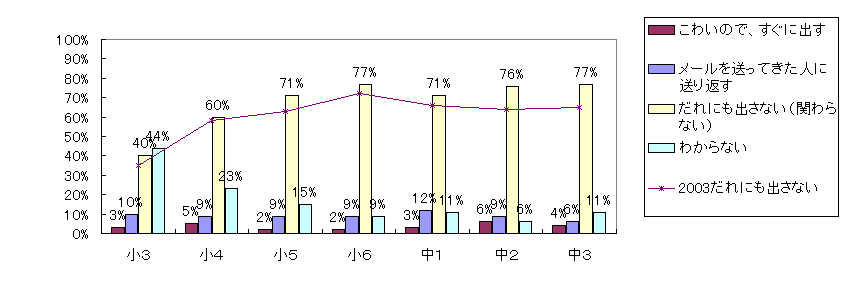
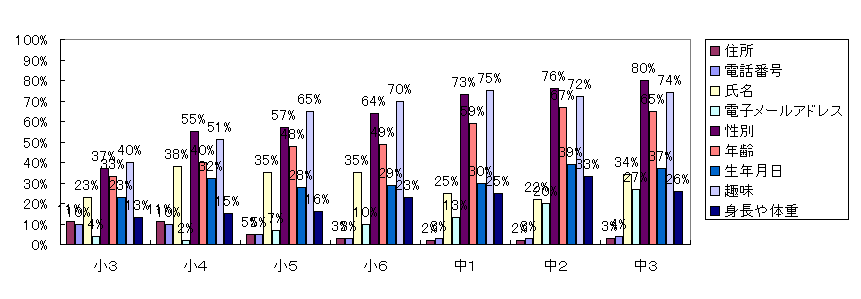
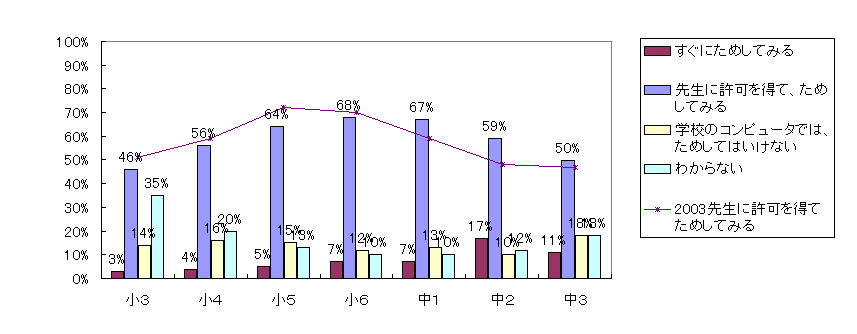
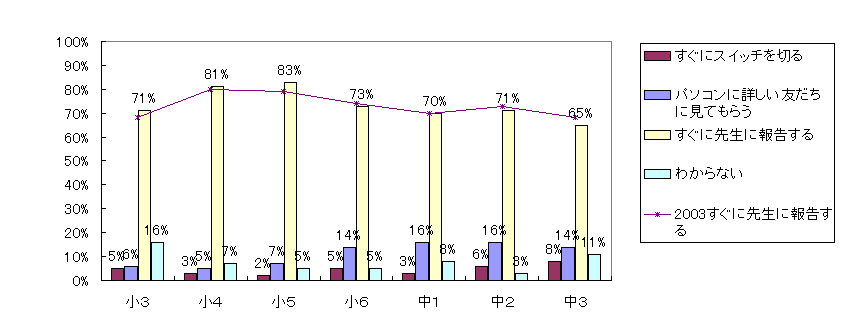
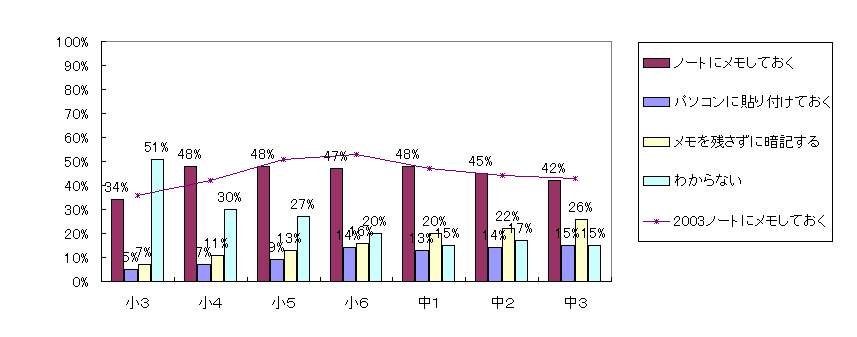 |
|||
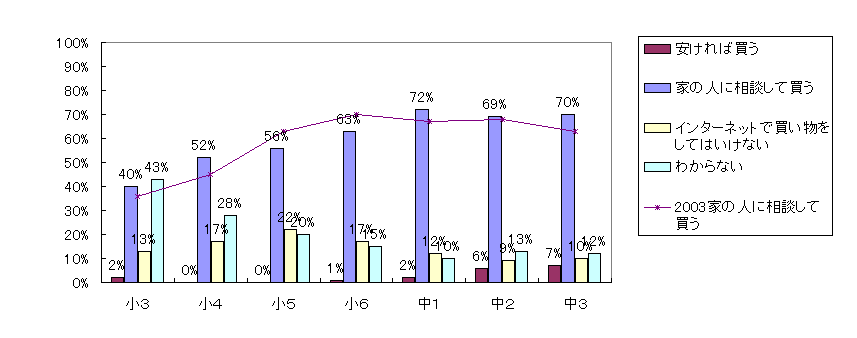
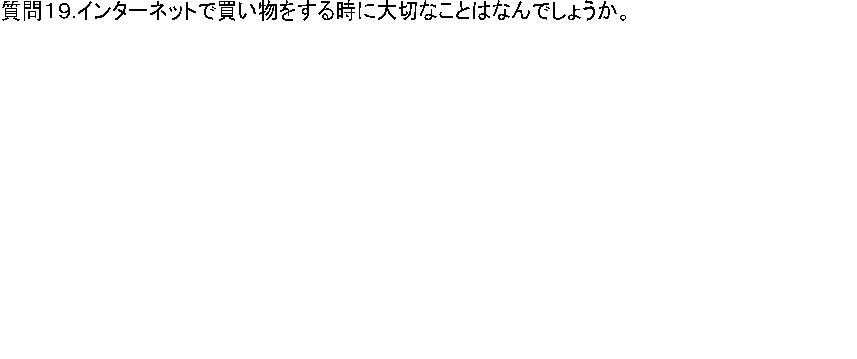
�@�e���������z���v���������X��������ƁA���w�Z�����w�N�����_���R�Ȃ�ɂȂ��Ă���O���t�i���l���X���j�������A����������ɂ��Ă��w�N�����������x�������킩��B
�@���z���v����������N�����l�Ɣ�r����ƁA���w�Z�P�N���̃f�[�^���قƂ�ǂ���������N��������Ă���A�����w�N���ق���N�x�ȏ��������ƂȂ��Ă��邱�Ƃ���������������������݂���B�������A�ǂ����ɂ��o���c�L�������A�������������k�����炩���s�K�����v�����������Ă��邱�Ƃ���������������������s�\���Ƃ�������B
�@������N�������}�����L����������Ă���A�u���O��A�o�^�[�Ȃǂ̃R�~���j�P�[�V�����c�[���ɂ��Ă��C�ɂȂ�Ƃ���ł���A�u����������������v���O�����Ȃ��ƃR�~���j�P�[�V�����c�[������s���ƍ��������ɂȂ��댯�������ł���B�������������p�ɂ��Ă������E�����������߂��K�v��������v����B