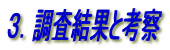 |
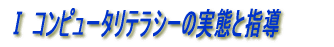 |
| 亂愝栤偵偮偄偰亃 |
| 彫拞妛峑偱嫵堢梡僐儞僺儏乕僞偺惍旛偑恑傒丄妛廗妶摦偵偍偄偰僐儞僺儏乕僞偑峀偔巊傢傟丄傑偨丄壠掚偱偺晛媦傕栚妎傑偟偄尰嵼丄帣摱丒惗搆偺僐儞僺儏乕僞儕僥儔僔乕偺幚懺傪攃埇偟丄崱屻偺巜摫偵惗偐偟偰偄偔偙偲傪栚揑偵丄愝栤傪愝掕偟偨丅 |
|
| 幙栤侾丏乽偱偒傞偙偲乿傪慡偰慖傫偱偔偩偝偄丅 |
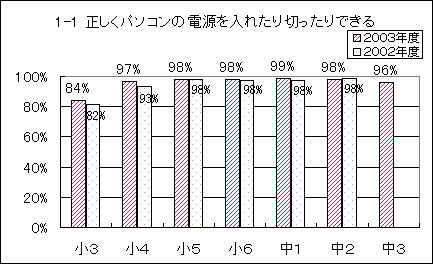 |
彫係埲忋偼丄傎傏侾侽侽亾偲峫偊偰傛偄儗儀儖偵払偟偰偄傞丅
巕偳傕偨偪偵偲偭偰偼僐儞僺儏乕僞偑傛傝恎嬤側傕偺偵側傝丄僥儗價偺僗僀僢僠傪擖傟傞條側姶妎偵嬤偯偄偰偒偰偄傞偺偱偼側偄偐丅 |
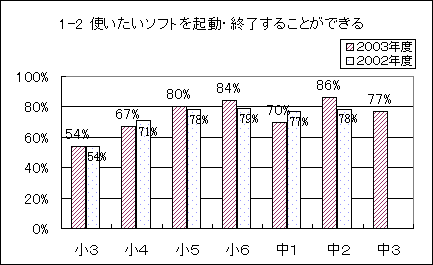 |
嶐擭搙偲偺斾妑偱偼丄偦傟傎偳戝偒側曄壔偼傒傜傟側偄偑丄彫妛峑偱偼弴挷側塃尐忋偑傝偵側偭偰偄傞丅
偄傠傫側僜僼僩傪巊偭偰傒偨偄偲偄偆巕偳傕払偺梸媮偵嫵巘懁偑摎偊偰偄傞偙偲傗妛廗偵妶梡偱偒傞懡條側僜僼僩偑摫擖偝傟偰偒偰偄傞昞傟偱偼側偄偐丅 |
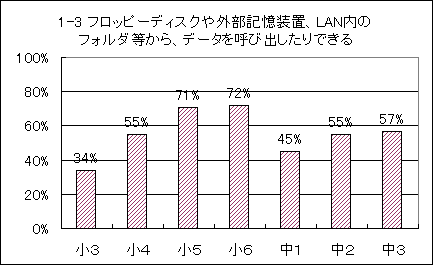 |
彫丒拞妛峑偦傟偧傟偵丄妛擭偵偁傢偣偰塃尐忋偑傝偵側偭偰偄傞丅
僜僼僩偵傛偭偰偼曐懚愭偑帺摦揑偵愝掕偝傟傞傕偺傕懡偔丄巕偳傕払偼乽曐懚乿偲偄偆嶌嬈偼偟偰偄偰傕丄擟堄偺応強偵僨乕僞傪曐懚偟偨傝丄偦偙偐傜屇傃弌偟偨傝偟偰偄傞偲偄偆堄幆偑敄偄偺偱偼側偄偐丅
仸拞妛峑偱偺悢抣偺掅壓偼彫丒拞妛峑偱愝栤偺暥復昞尰偑堘偭偨偨傔丄撪梕傪擄偟偔懆偊偨寢壥偲峫偊傜傟傞丅 |
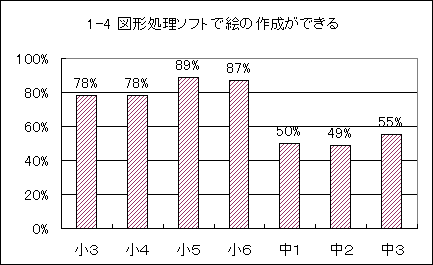 |
彫妛峑偱崅偄悢抣傪帵偟偰偄傞偺偼丄僐儞僺儏乕僞妛廗偺擖栧婜偲偟偰丄偍奊偐偒僜僼僩偑峀偔巊傢傟偰偄傞偙偲偺昞傟偲峫偊傜傟傞丅
拞妛峑偱悢抣偺掅壓偑傒傜傟傞丅傕偪傠傫拞妛惗傕彫妛峑偱偺宱尡偐傜偍奊偐偒僜僼僩側偳偱偺嶌恾偼偱偒傞偲峫偊傜傟傞偑丄乽恾宍張棟僜僼僩乿偲偄偆尵梩傪擄偟偔懆偊偰偟傑偭偨偐丄偁傞偄偼丄庼嬈応柺偱偺妶梡偑彮側偄偙偲偑尨場偱偼側偄偐丅
|
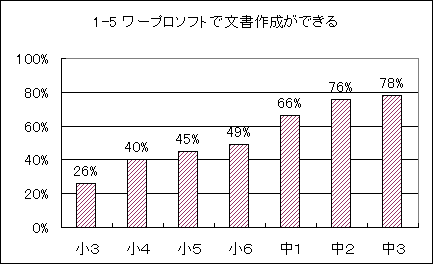 |
彫丒拞妛峑傪捠偠偰拝幚偵悢抣偑忋偑偭偰偄傞丅
彫妛峑偱偼丄儘乕儅帤妛廗傗埬撪忬傪僐儞僺儏乕僞偱嶌偭偨傝偲偄偭偨妶梡偑峀傑傝丄偝傜偵拞妛峑偱偼丄媄弍丒壠掚偺庼嬈偵儚乕僾儘僜僼僩傪庢傝擖傟偰偄傞妛峑傕懡偔丄暥帤擖椡偺婡夛偑懡偔側偭偰偒偰偄傞偲巚傢傟傞丅 |
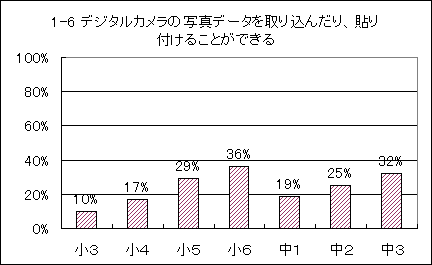 |
妛擭偵偁傢偣偰悢抣偼忋偑偭偰偄傞丅偨偩偟丄慡懱揑偵掅偄抣偲側偭偨丅
嶣偭偨幨恀傪帒椏偲偟偰報嶞偟偰丄宖帵偟偨傝丄採帵偟偨傝偲偄偆抜奒偵偲偳傑偭偰偄傞丅
傑偢偼丄巜摫偡傞嫵巘懁偺儕僥儔僔乕偺岦忋偑朷傑傟傞丅 |
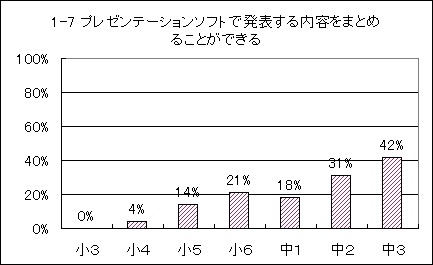 |
悢抣偼掅偄傕偺偺丄彫丒拞妛峑偦傟偧傟偵丄妛擭偵偁傢偣偰塃尐忋偑傝偵側偭偰偄傞丅
憤崌妛廗偺傑偲傔傗敪昞偵妶梡偝傟傞働乕僗偑彊乆偵憹偊偰偒偰偄傞偺偱偼側偄偩傠偆偐丅 |
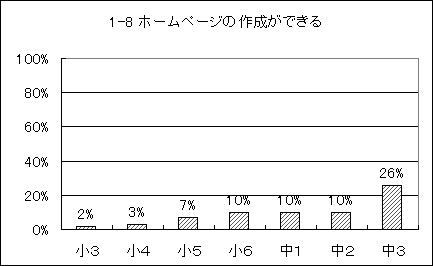 |
屻偺乽幙栤係丂庼嬈偱妛廗偟偨撪梕乿傛傝傕悢抣偑崅偄妛擭偑偁傞丅壠掚偱屄恖偺儂乕儉儁乕僕嶌惉偵庢傝慻傫偱偄傞巕偳傕偑偄傞偙偲偺昞傟偲峫偊傜傟傞丅 |
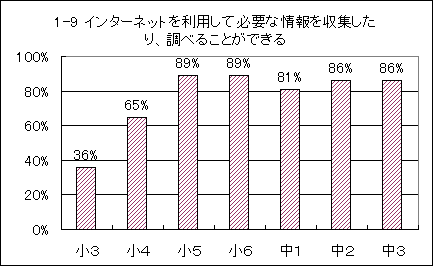 |
彫妛峑偺崅妛擭偐傜丄條乆側嫵壢偱忣曬廂廤偺庤抜偲偟偰戝偄偵妶梡偝傟偰偄傞偲偄偆尰忬偐傜丄偦傟偵敽偄悢抣傕崅偔側偭偰偒偰偄傞丅 |
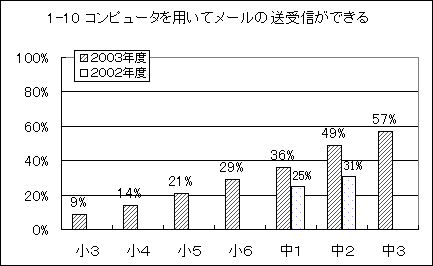 |
屻偺乽幙栤係丂庼嬈偱妛廗偟偨撪梕乿傛傝傕悢抣偑崅偔側偭偰偄傞丅傑偨丄拞侾丒俀偱偼丄嶐擭搙傛傝傕悢抣偑忋偑偭偰偄傞丅
壠掚偱偺僐儞僺儏乕僞偲僀儞僞乕僱僢僩娐嫬偺晛媦偑偝傜偵恑傫偩偙偲偵傛傝丄壠掚偱儊乕儖傪妶梡偡傞婡夛偑憹偊偰偒偰偄傞偙偲偑昞傟偨悢抣偱偁傠偆丅 |
|
| 幙栤俀丏晛抜偳傫側曽朄偱暥帤擖椡傪偟偰偄傑偡偐丅 |
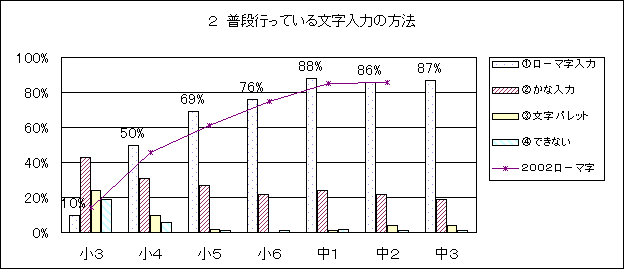 |
| 儘乕儅帤傪妛廗偡傞係擭惗偐傜丄儘乕儅帤擖椡偑偐側擖椡傪媡揮偟偰偄傞丅彫妛峑崅妛擭偐傜偼丄傎偲傫偳偺巕偳傕偑壗傜偐偺曽朄偱暥帤傪擖椡偡傞偙偲偑偱偒偰偄傞偙偲偑傢偐傞丅 |
|
| 幙栤俁丏巊偆偙偲偺偱偒傞傕偺傪慡偰慖傫偱偔偩偝偄丅 |
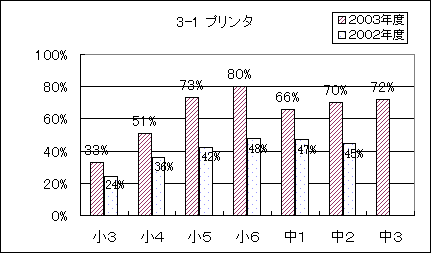 |
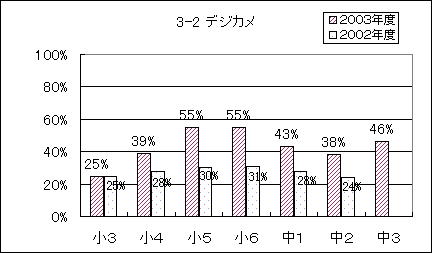 |
| 廃曈婡婍偲偟偰丄僾儕儞僞傗僨僕僞儖僇儊儔偺妶梡搙偑慜擭偵斾妑偟偰戝偒偔怢傃偰偄傞丅僾儕儞僞偵偍偄偰偼丄僀儞僞乕僱僢僩偱廤傔偨忣曬帒椏偺報嶞傗丄帺暘偺嶌昳偺報嶞側偳丄妶梡偡傞婡夛偑懡偔側偭偰偄傞偙偲偑峫偊傜傟傞丅僨僕僞儖僇儊儔偼丄憖嶌偑娙扨偱偁傞偙偲偐傜尒妛摍偱巕偳傕偨偪偑帺桼偵妶梡偡傞婡夛偑憹偊偰偒偰偄傞偙偲偵傛傞怢傃偲峫偊傜傟傞偑丄棙梡偱偒傞戜悢偑崱傛傝傕憹偊傟偽丄偝傜偵悢抣偑崅偔側偭偰偄偔偙偲偑婜懸偱偒傞丅 |
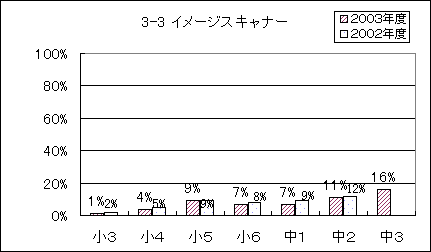 |
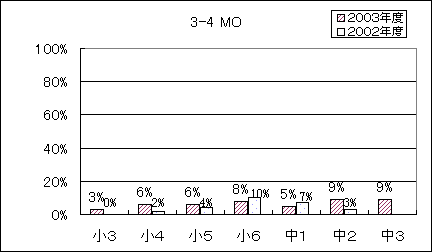 |
| 庡偵嫵巘懁偑帒椏嶌惉傗僨乕僞娗棟偺偨傔偵妶梡偡傞婡婍偱偁傞偙偲偐傜丄巕偳傕払偑捈愙棙梡偡傞婡夛偼彮側偔丄摉慠丄悢抣偼掅偔側偭偰偄傞丅妶梡偺婡夛傪憹傗偟偰偄偔偨傔偵偼嫵巘懁偺儕僥儔僔乕岦忋偑昁梫偲側傞丅 |
|
| 幙栤係丏庼嬈偱妛廗偟偨撪梕傪慡偰慖傫偱偔偩偝偄丅 |
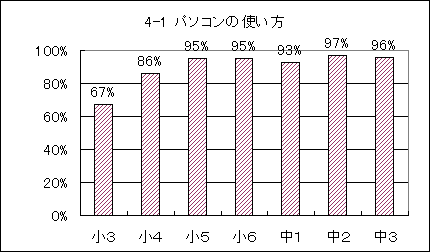 |
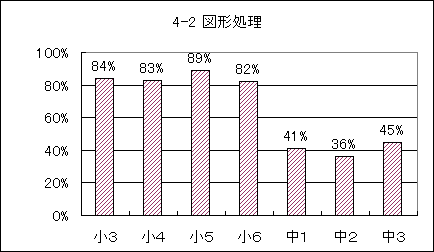 |
| 奺峑偛偲偺僨乕僞偵栚傪岦偗偰傒傞偲丄彫妛峑崅妛擭偐傜偼丄偡傋偰偺妛峑偱僷僜僐儞偺妛廗偑峴傢傟偰偄傞偙偲偑傢偐傞丅偁偊偰栤戣揰傪巜揈偡傟偽丄彫妛峑侾擭惗偐傜奺峑偱掕傔偨巜摫寁夋偵増偭偰妛廗偑恑傔傜傟傟偽丄彫俁偱傕侾侽侽亾偵嬤偄悢抣偑婜懸偱偒傞偺偱偼側偄偩傠偆偐丅 |
彫妛峑偱偼庡偵摫擖抜奒偱偍奊偐偒僜僼僩偑妶梡偝傟偰偄傞働乕僗偑懡偄偨傔丄崅偄悢抣偵側偭偰偄傞丅拞妛峑偱偼敪揥揑偵妶梡偟偰偄傞応崌偑懡偔丄傾儞働乕僩偺幙栤撪梕傕崅搙側撪梕傪婜懸偟偰偄傞傛偆偵偲傟傞偨傔悢抣偑壓偑偭偰偄傞偲巚傢傟傞丅 |
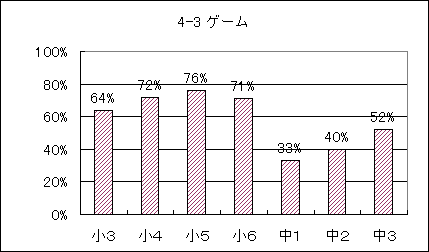 |
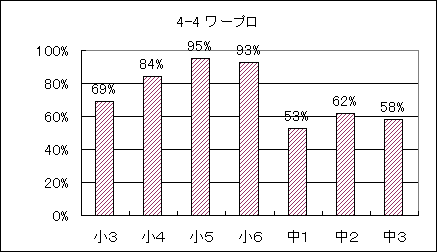 |
| 彫妛峑偱偼巕偳傕払偺嫽枴丒娭怱傪崅傔傞偨傔偵庼嬈偱埖偆偙偲働乕僗偑懡偄偙偲偺昞傟偲峫偊傜傟傞丅媡偵拞妛峑偱偼偦偺抜奒偼挻偊偰偄傞偲峫偊傜傟傞偺偱丄摉慠丄悢抣偼壓偑傞丅 |
彫妛峑崅妛擭偱偺悢抣偺崅偝偼丄僐儞僺儏乕僞偑嶌昳傗儗億乕僩丄敪昞帒椏偺嶌惉側偳丄傑偲傔傞抜奒偱傕妶梡偝傟偰偍傝丄昁慠揑偵庼嬈偵傕庢傝擖傟傜傟偰偒偰偄傞偙偲偺昞傟偱偁傠偆丅拞妛峑偱偼庢傝棫偰偰庼嬈偱偼埖傢偢丄懠偺僜僼僩傊偺暥帤擖椡偲偄偭偨敪揥揑側妛廗偵恑傫偱偄傞偨傔偵掅傔偺悢抣偲側偭偰偄傞偲峫偊傜傟傞丅 |
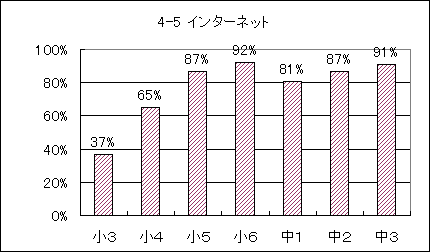 |
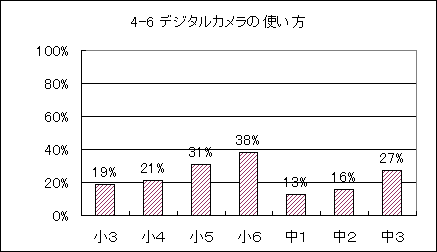 |
| 彫妛峑抜奒偱丄俋侽亾埲忋偺巕偑宱尡偟偰偄傞丅憤崌揑側妛廗側偳偵偍偄偰丄巕偳傕払偺庡懱揑側挷傋妛廗側偳偵寚偐偣側偄傕偺偵側偭偰偒偰偄傞偙偲偼柧傜偐偱偁傞丅 |
俇擭惗抜奒偱傕俁俉亾偵偲偳傑偭偰偄傞丅婡婍偲偟偰偺庤寉偝傪峫偊傞偲丄傕偭偲妛廗応柺丄巊梡婡夛偑憹偊偰傎偟偄丅偦偺偨傔偵偼戜悢傪憹傗偡偲偄偭偨僴乕僪柺偺壽戣傕巆偝傟偰偄傞丅 |
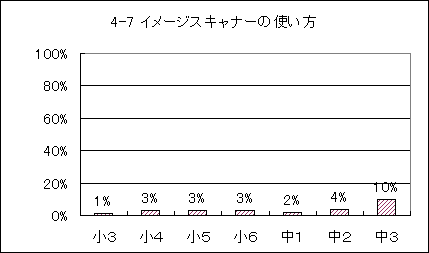 |
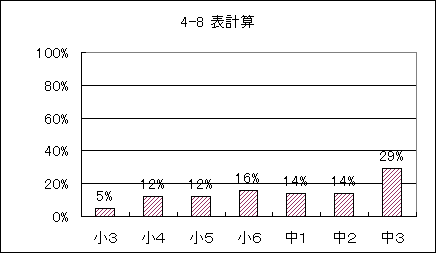 |
| 巕偳傕偑捈愙憖嶌偡傞婡夛偑彮側偄婡婍側偺偱丄昁慠揑偵庼嬈偱庢傝忋偘傜傟傞偙偲傕彮側偄丅 |
拞妛峑偱偼嫵壢妛廗偺拞偱丄昁梫偵墳偠偰妶梡偝傟偨椺偑偁偭偨傕偺偲巚傢傟傞丅 |
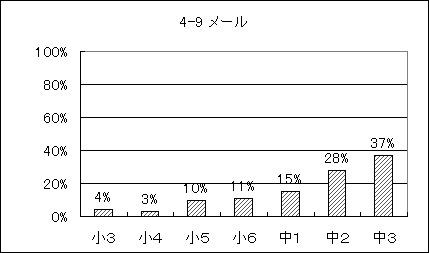 |
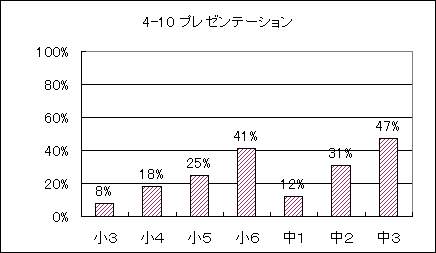 |
| 摿偵彫妛峑偱偼丄奜晹偲偺岎棳偲偄偆揰偱惂栺傕懡偔丄戝偒側峀偑傝偵偼側偭偰偄側偄傛偆偩丅嶳宍巗偺忣曬僱僢僩儚乕僋偺妶梡傪婜懸偟偨偄丅拞妛峑偱偼塸岅偺庼嬈偺堦娐偲偟偰奀奜傊偺儊乕儖傪庢傝擖傟偰偄傞妛峑傕偁傞丅忣曬儌儔儖偺巜摫偱偺妶梡傕傒傜傟傞丅 |
彫丒拞妛峑偲傕嵟崅妛擭偱偺悢抣偑崅偄丅偙傟傑偱愊傒忋偘偰偒偨傕偺傪惗偐偟丄妛廗偺傑偲傔偺庤抜偲偟偰妶梡偝偣偨偄偲偄偆嫵巘偺巚偄偑斀塮偟偰偄傞偲峫偊傜傟傞丅 |
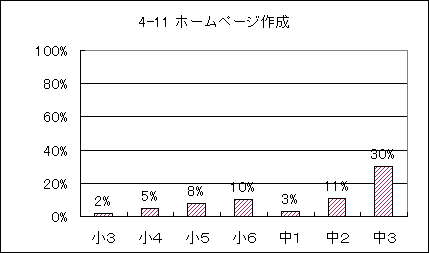 |
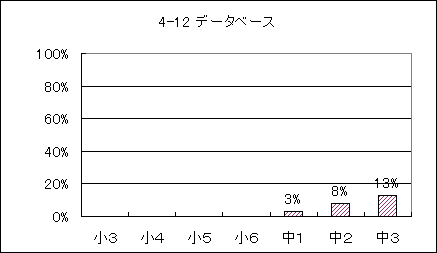 |
| 傑偩傑偩悢抣偼掅偄偑丄忣曬敪怣偺敪揥揑側庤抜偲偟偰庢傝擖傟偰傞椺偑彊乆偵弌偰偒偰偄傞偙偲偺昞傟偱偁傠偆偐丅妛峑偺HP偵巕偳傕払偑嶲壛偟偰偄傞働乕僗傕傒傜傟傞丅 |
慡懱偲偟偰偺宱尡偼彮側偄偑丄堦晹丄拞妛峑偺媄弍壠掚偺庼嬈偱庢傝擖傟傜傟偰偄傞椺偑傒傜傟傞丅 |
|
| 亂丂峫丂嶡丂亃 |
丂嶐擭搙偲斾妑偱偒傞崁栚偵偮偄偰偼丄傎傏慡偰偺悢抣偑嶐擭搙傛傝傕忋夞偭偰偄傞丅偙傟偼丄僐儞僺儏乕僞偺婎杮憖嶌偺妛廗偑懡偔偺妛峑偱幚巤偝傟偨寢壥偱偁傝丄妛峑尰応偱偺昁梫姶偺崅傑傝偲愭惗曽偺搘椡偺惉壥偺昞傟偱偁傞偲峫偊傜傟傞丅傑偨丄嫵壢偺妛廗偺拞偵傕僐儞僺儏乕僞偺妶梡偑怹摟偟偰偒偰偍傝丄昁慠揑偵儕僥儔僔乕偑崅傑偭偨寢壥偲傕撉傒庢傞偙偲偑偱偒傞丅偨偩偟丄摿偵彫妛峑偺嫵壢偱妶梡偝傟傞応崌偼丄摨偠妛廗撪梕偱偁偭偰傕妛廗偺恑傔曽傗傑偲傔曽丄偁傞偄偼巜摫幰偵傛偭偰丄僐儞僺儏乕僞偺妶梡傪宱尡偡傞巕偲偟側偄巕偑惗偠偰偟傑偆壜擻惈偑偁傝丄偦偺屻偺僨僕僞儖僨僶僀僪傊偮側偑傞婋尟惈傕娷傫偱偄傞丅婎杮揑側憖嶌偵偮偄偰偼丄偳偺巕傕暯摍偵宱尡偟偨傝丄恎偵偮偗偨傝偱偒傞傛偆偵丄奺峑偺巜摫寁夋偵婎偯偄偨懌暲傒傪懙偊偨妛廗偑昁梫偱偁傞丅
丂傑偨丄拞妛峑偵偍偄偰偼丄彫妛峑偱傎偲傫偳偺巕偑偙偙傑偱偺儕僥儔僔乕傪恎偵偮偗偰偒偰偄傞偼偢偩偲偄偆慜採偵棫偰傟偽丄僗僞乕僩儔僀儞傪崱傛傝傕崅偔愝掕偟丄偦偺暘丄懡條側妶梡偵偮側偘偰偄偔偙偲傕婜懸偱偒傞偺偱偼側偄偩傠偆偐丅 |
|
|
|