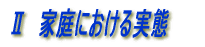 |
| 【設問について】 |
| 学校でパソコンやインターネットの使い方を指導している一方で、家庭に帰った子ども達がどの程度パソコンを利用しているのか実態を調査するとともに、インターネットでのトラブルが増加している今、山形市の子ども達のインターネットや携帯電話・PHSの利用状況を把握したり、有害サイトやインターネットカフェなどの利用について調査する。 |
|
| 質問5.家でパソコンが使えますか。 |
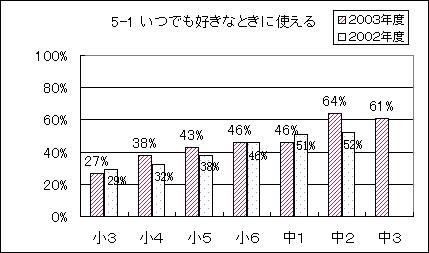 |
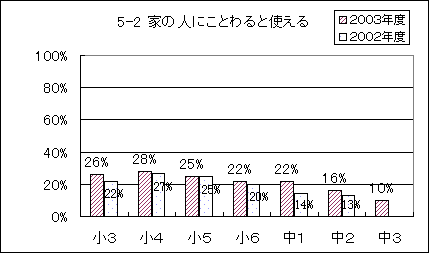 |
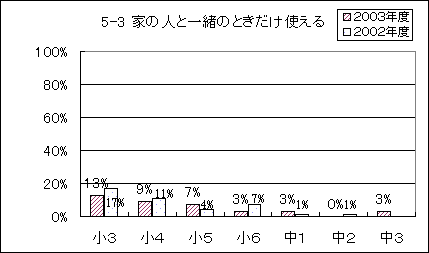 |
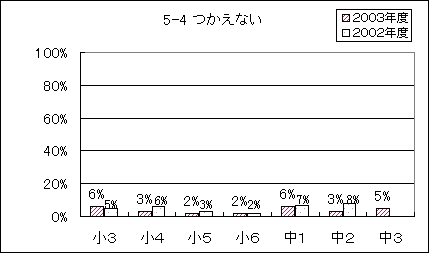 |
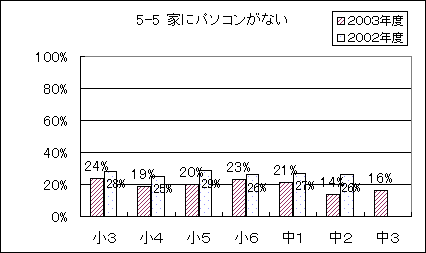 |
およそ学年が進むにつれて割合が高くなっていく。昨年の学年との比較をすると、前年の約10%増というところか(小6~中1を除く)。小4、小5、中2では昨年の同学年の結果よりも値が高く
、家庭でのパソコンの使用がすすんでいることがわかる。
また、家庭でパソコンを使用する環境が整い、特に中学校2年生では8割の生徒が家庭でパソコンを使用している。
総合すると、家にパソコンのない家庭がどの学年も減少していることより、各家庭にパソコンが確実に浸透してきていることがわかる。そして「家の人にことわると使える」「いつでも好きなときに使える」が昨年と比べて増加傾向にあり、子ども達の家庭でのパソコンの使用機会が増えていることが伺える。 |
|
| 質問6.自分が自由に使える携帯電話(PHSを含む)を持っていますか。 |
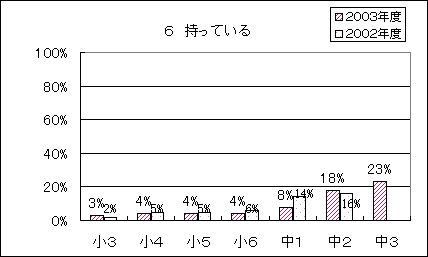 |
昨年に比べて大きな変化は見られない。今年新たに中3の実態を調査したが、予想通り中2の結果を上回った。
小学校と中学校との数字を比較すると、小学生の時は学年による所持率の差はあまり見られない、それに対し中学校は学年が進むにつれて増加している。また、中1と小6を比較すると所持率が2倍となり、中3は4、5人に1人が携帯電話を持っていると考えてよいだろう。中学生になることで、家庭の考え方も変化していると思われる。 |
|
| 質問7.家でインターネットができますか。 |
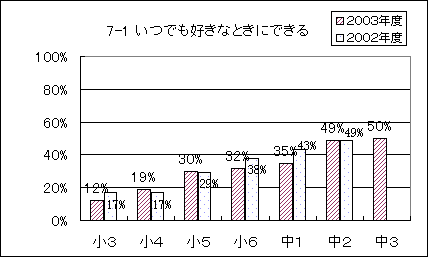 |
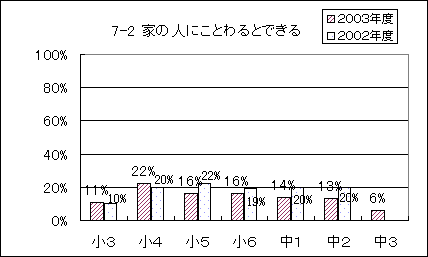 |
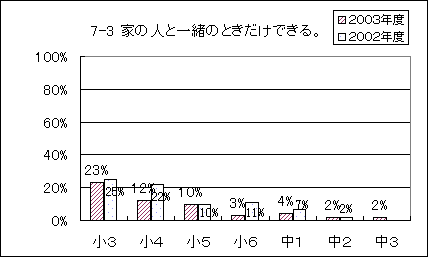 |
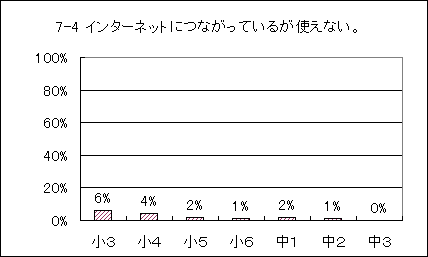 |
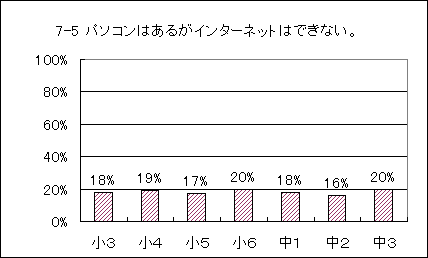 |
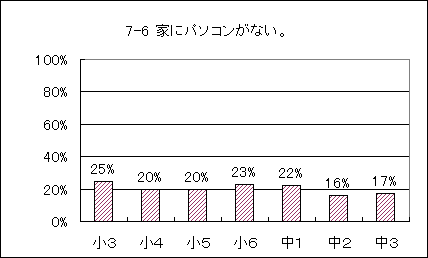 |
「いつでも好きなときにできる」との問いでは、昨年同様、学年が進むにつれて増加していることがわかる。中3では半数の生徒が家庭で自由にインターネットを使用していることがわかる。また小3で46%が家庭でインターネットを利用していることもわかった。
また、(7-2)、(7-3)の結果から、学年が進むにつれて家庭での制約が少なくなっているようだ。インターネット接続の普及率を見ると、学年に関係なく20%前後を推移している。 |
|
| 質問8.家でインターネットをどのくらい使っていますか。 |
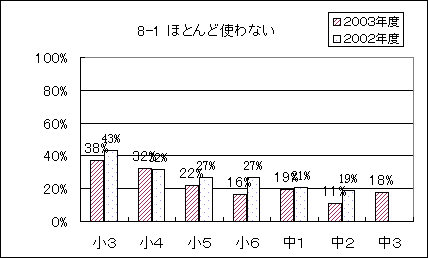 |
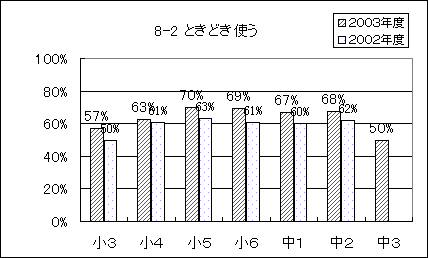 |
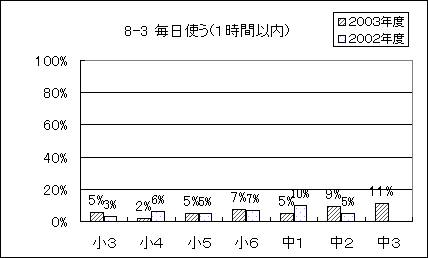 |
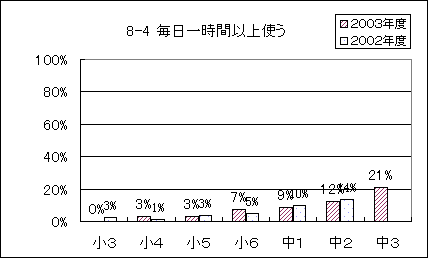 |
家庭でインターネットを利用できる児童生徒に対しての設問であるが、昨年と比較して、ほとんど使わない児童生徒が減少し、学年を追うごとにインターネットを使用している実態が読み取れる。
毎日使用する児童生徒は小6から徐々に増え、中3になると30%を超えている。昨年度のデータとの比較をすると大きな変化は見られない。また毎日一時間以上使用する児童・生徒も学年を追うごとに増え、視力等の健康面での悪影響も懸念される。 |
|
| 質問9.家でインターネットをするときに、家の人との約束事を決めていますか。 |
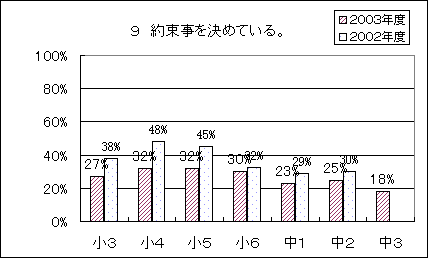 |
昨年の同学年との比較で、どの学年も約束事の有無は減少傾向にあり、それが学年を追うごとに減る傾向がある。年を追うごとに自由にインターネットが使える割合が増加し、約束事が希薄になっている現状がうかがえる。 |
|
| 質問10.家のパソコンや携帯電話を使って、インターネットで見たことや利用したことがあるものをすべて選びましょう。(複数回答あり) |
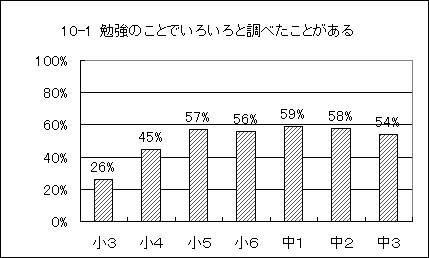 |
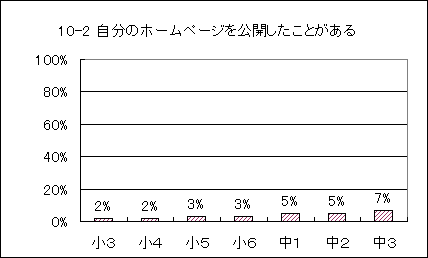 |
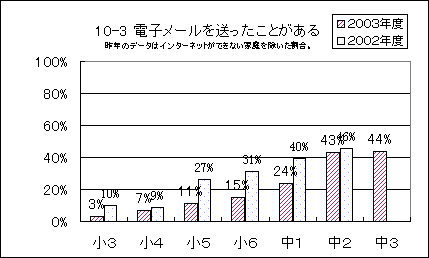 |
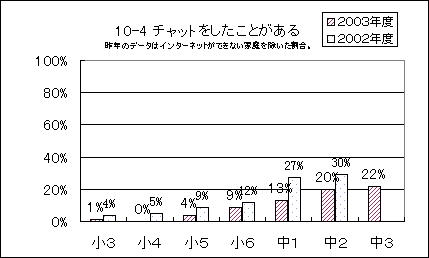 |
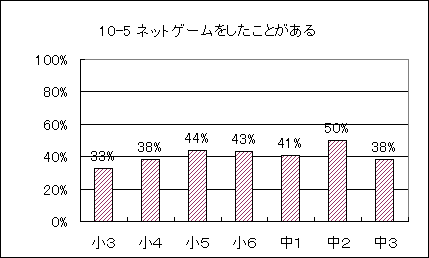 |
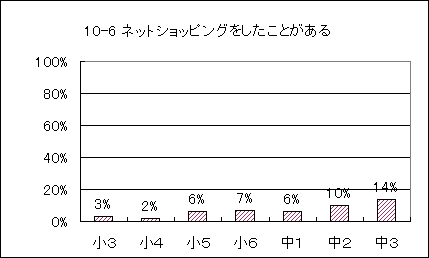 |
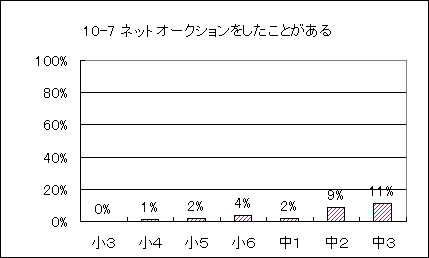 |
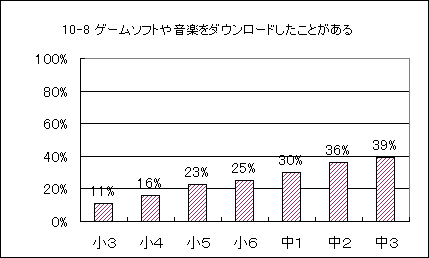 |
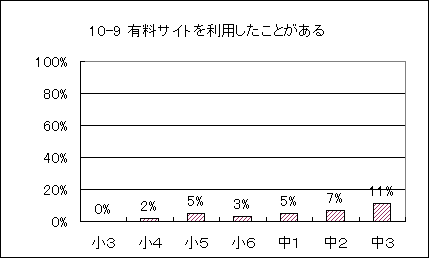 |
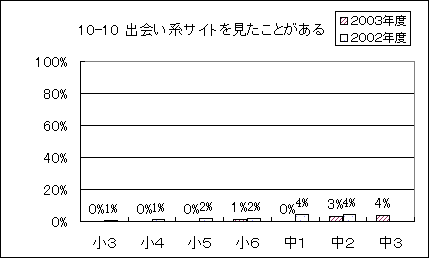 |
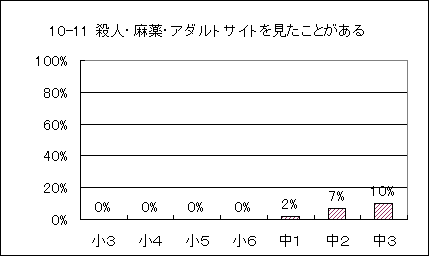 |
(10-1)勉強での使用は小4から急速に増加し、各学年5~6割で落ち着いている。これはパソコンがないまたは使えない割合を考えると、大変よく使用していることがわかる。
(10-2)自分のホームページ公開は緩やかながら、確実に学年を追うごとに増加傾向にあるが、ほとんど公開されていないようである。
(10-3)電子メールの使用は学年が進むにつれて増加している。特に中2から大きな伸びが見られ、マナーやモラルについて指導を強化する必要がある。
(10-4)危険性を高いチャットの経験は学年が進むにつれて多くなっている。中学生の値が20%に達し、中2・3で5人に1人の経験がある。
(10-5)ネットゲームは想像以上に多い。特に小3から30%を越える。パソコンはゲーム機というイメージが大きいようだ。
(10-6,7)ネットショッピングやネットオークションも数値は小さいが小3から経験しているようだ。これもおよそ学年が進むにつれて増加傾向にある。詐欺なども少なからず横行しているが、その危険性を子ども達はどれだけ認識しているか疑問である。
(10-8,9)ゲームソフト等のダウンロードや有料サイトでは後に高額なお金を要求されたり、ウィルスの危険性などがある。これも学年を追うごとに割合が高くなっていく。ダウンロードでは小3でも約一割が経験している。有料サイトも少ないながらも学年の低い小学生も経験していることがわかる。
(10-10)「出会い系サイトを見たことがある」は大きな増減は見られないが、中学生の利用が見られるため指導が必要である。
(10-11)「殺人・麻薬・アダルトサイトを見たことがある」は初めての調査だが、中1から割合が増加傾向にある。モラル面での指導が必要である。
(10-12)「インターネットカフェを利用することがある」は最近、問題になっている場所であるが、小学生で経験している児童がいることがわかる。最近では個人情報(ID、パスワード等)を盗むなど犯罪が多発しており、インターネットカフェは18歳未満は深夜立ち入り禁止にもなっている。しかし、中学生では学年を追うごとに増加傾向にあるため指導が必要である。 |
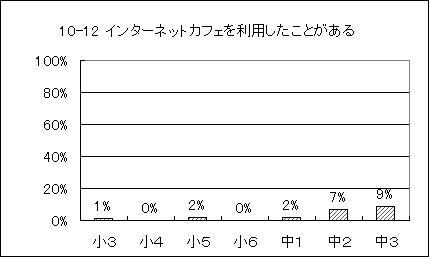 |
|
| 【 考 察 】 |
パソコンの家庭での使用は、昨年に比べても増加傾向にある。しかしながらパソコンを持たない家庭やインターネット未接続の家庭はどの学年も同じような割合で推移し、デジタルディバイドが広がる要因の一つと考えられる。児童・生徒のインターネット使用率が高くなっているが、家庭での約束事や決まりは学年を追うごとに希薄になってきており、情報モラルやマナーの指導の充実が求められる。インターネットを利用した様々なサービスやショッピングは非常に便利なものであるが、反面子どもたちはその危険性に気づかずに使用していると考えられる。今までと違った形の犯罪が広がりを見せている中で、その危険性に教師も親も気づき、子どもたちに指導していくとともに、子どもたち自身にも利用の仕方を考えさせる必要があろう。
|
|
|
|