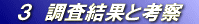 |
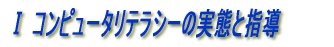 |
| 【設問について】 |
小・中学校の教育用コンピュータの整備がさらに進み、学習活動においてコンピュータが広く使われ、また、家庭での普及も目覚ましい現在、児童・生徒のコンピュータリテラシーの実態を把握し、今後の指導に生かしていくことを目的に、設問を設定した。
尚、児童・生徒に意味がより伝わりやすいように質問の文言は若干修正したが、年度ごとの推移をつかみたいというねらいがあることから、質問の項目は平成15年度から3年間、踏襲している。 |
|
質問1.「できること」を全て選んでください。  2004年度 2004年度  2005年度 2005年度 |
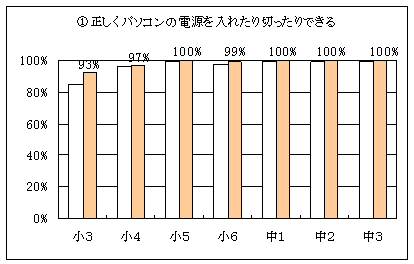 |
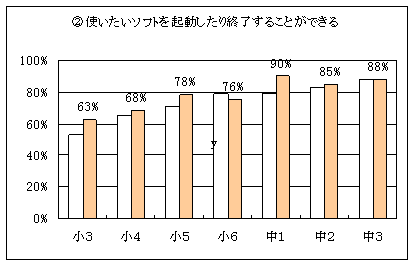 |
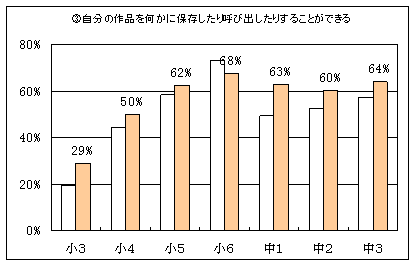 |
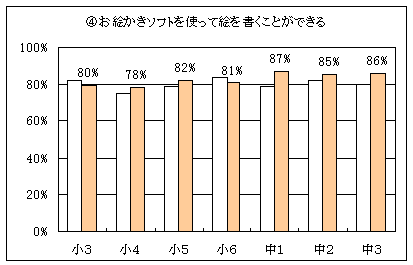 |
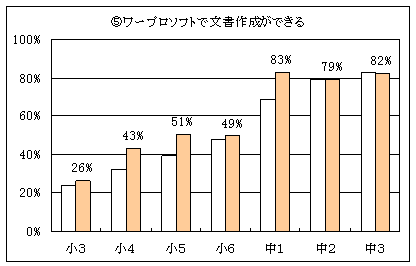 |
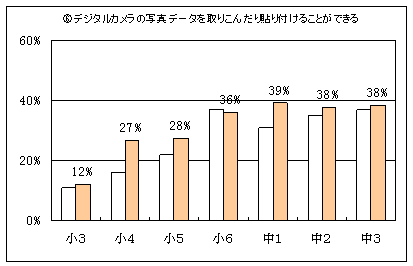 |
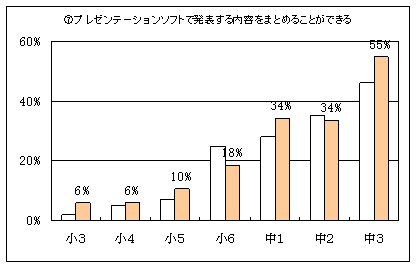 |
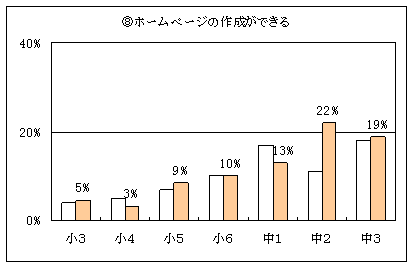 |
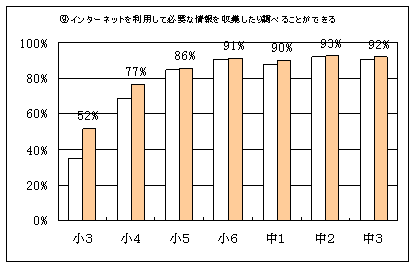 |
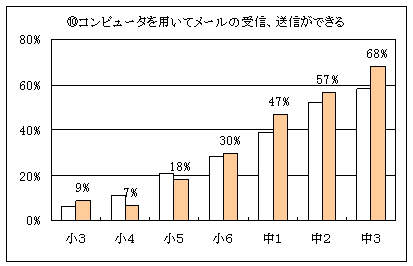 |
学年によるばらつきはあるものの、家庭での利用がさほど多いとは考えられないプレゼンテーションソフトについての数値も上がっている。これは、学習のまとめの発信方法として、授業での活用が増えてきていることを示していると考えられる。「もともとできる子」ではなく、「学校での学習」によってリテラシーが高まってきていることが現れた数値の一つと捉えたい。
メールに関する数値が順調な右肩上がりに推移している。個人的な活用に加え、中学校のカリキュラムに位置づけられ、計画的に学習し、確実に身に付いてきている現れであろう。 |
|
| 質問2.普段どんな方法で文字入力をしていますか。 |
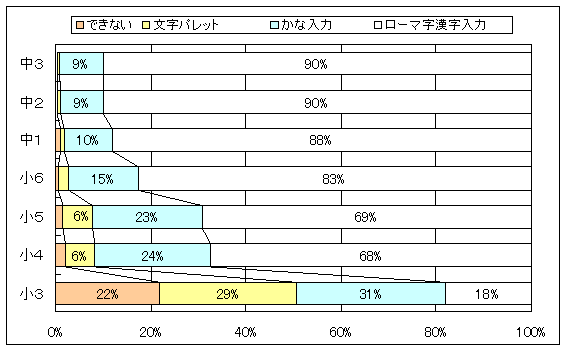 |
ローマ字を学習する4年生から、ローマ字入力がかな入力を逆転しているのは例年みられる傾向である。
中学生の段階では、ほとんどがローマ字入力に移行していることがわかる。 |
|
質問3.使うことのできるものを全て選んでください。  2004年度 2004年度  2005年度 2005年度 |
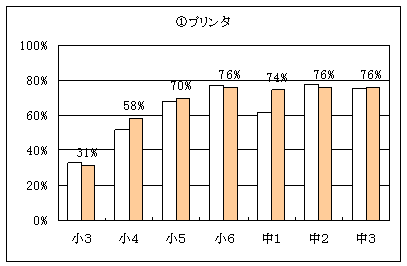 |
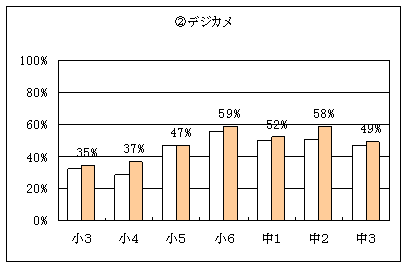 |
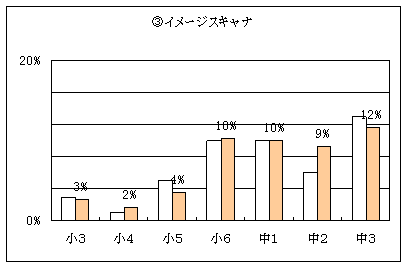 |
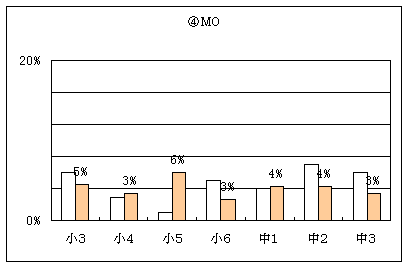 |
周辺機器のうちプリンタ、デジカメ、スキャナの活用度については昨年度との有意差はみられない。
プリンタでは、学年が上がるにつれて活用度が上がっていることから、インターネットで調べたことや自分が作った作品などを授業で印刷する機会が増えていることがわかる。
スキャナーは、操作方法がやや難しいため、小学生では主に教師が活用しているようだ。中学校では、資料をスキャンして自分のプレゼンテーションデータに貼り付けるなど、生徒自身の活用も増えているそうである。
MOは、学年が上がっても活用度は増えず、昨年度と比較してもむしろ減少傾向にある。CD-RやUSBメモリーなどが大容量メディアとしてMOに代わって活用されているのではないかと思われる。 |
|
質問4.授業で学習した内容を全て選んでください。  2004年度 2004年度  2005年度 2005年度 |
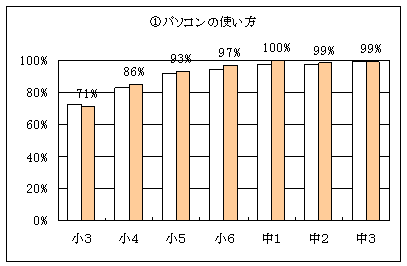 |
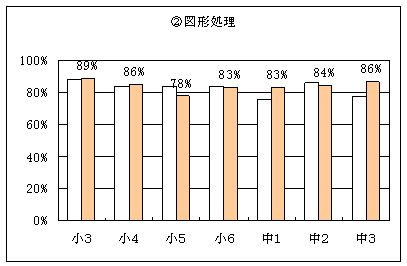 |
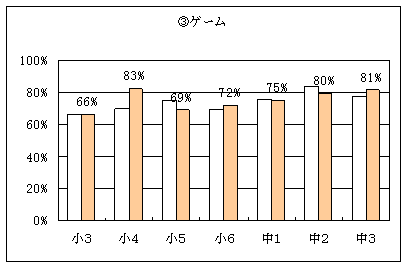 |
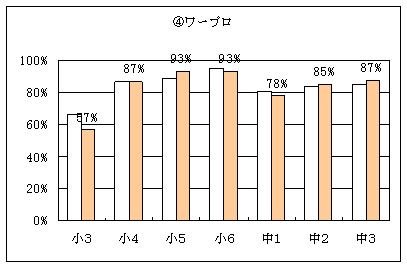 |
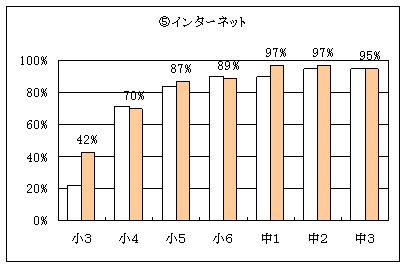 |
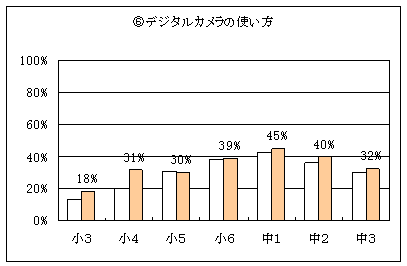 |
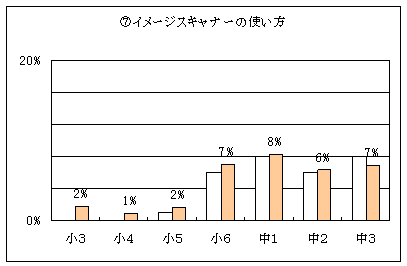 |
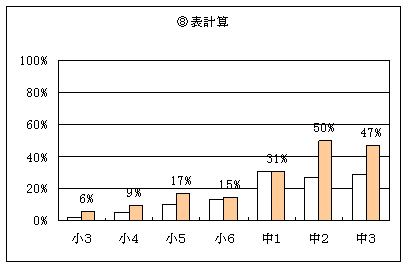 |
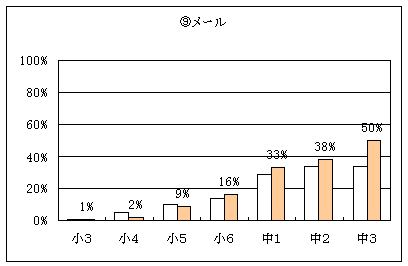 |
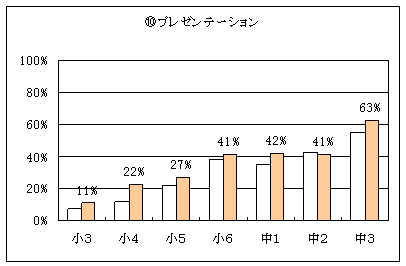 |
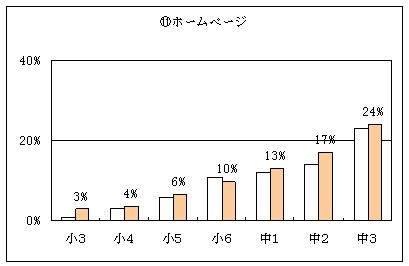 |
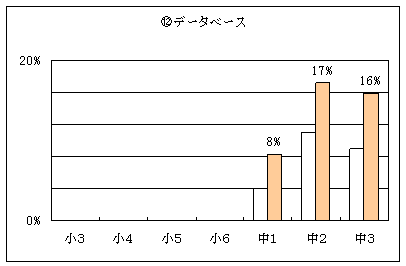 |
小学校の高学年からは、ほぼ全ての学校でパソコンの学習が行われていることがわかる。
学習する内容としては、導入でよく活用される図形処理やワープロ、インターネットが全体的に高い数値を示している。これらの中で、インターネットの活用に関して3年生において伸びが見られるが、さらに各教科や総合的な学習の時間などで積極的な活用を期待していきたい。
デジタルカメラの使い方については、これからも各学年においても活用頻度が増えてくるものと考えられるが、各学校に備えてある台数が子どもたちの活動を十分に満たしていないようであるので、ハード面で充実していく必要がある。
メールについては、中学校において伸びが見られ、授業の中で様々な関わりを持つ機会としてこれからもはば広い活用が期待される。 |
|
| 【 考 察 】 |
ここ数年の調査結果で、順調に数値が伸びてきている項目と頭打ちになっているものを分析すると、「児童・生徒」が直接操作する機器と、「教師」が管理し、操作する機器とが、特に小学校においてはっきりと分かれてきていることを読み取ることができる。こういった児童・生徒と教師の分業が進んできた背景としては、コンピュータの活用が「目的」よりも「手段」として定着してきたことが挙げれるのではないだろうか。
中学校では教科としてリテラシーを高めていくこと自体を「目的」とすることも可能であり、計画的、効果的に学習が進められてる。また、小学校では、様々な教科で調べたりまとめたりする学習の「手段」として活用されることが多く、純粋にリテラシーを高めるためにかけられる時間は限られているという現状がある。このことにより、「ここから先は子どもに教えずに教師が進めよう」「この機器は教師が操作したほうが効率がいい」という判断がなされ、子どもたちが使い方を学習する機器は自ずと限定されていると考えられる。
コンピュータが学習活動に確実に根付いてきた今こそ、児童・生徒の学習内容と照らし合わせ、本当に必要なリテラシーを系統的に整理し、実践されていくことが望まれるのではないだろうか。 |
|
|
|