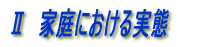 |
| 亂愝栤偵偮偄偰亃 |
|
| 幙栤俆丏壠偵僷僜僐儞偑偁傝傑偡偐丅 |
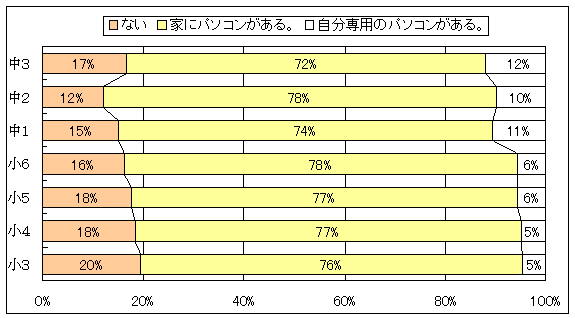 |
丂帺暘愱梡偺僷僜僐儞傪帩偪巒傔傞帪婜偑拞妛侾擭偑堦偮偺嫬奅偱偁傞丅彫妛掅妛擭傛傝嫽枴傗娭怱偺偁傞帣摱偼偦偺傑傑巊梡傪懕偗丄拞妛擖妛傪偒偭偐偗偵巊梡偟巒傔傞惗搆偑偱偰偒偰偄傞傛偆偱偁傞丅傑偨慡壠掚偺俉侽亾偵僷僜僐儞偑晛媦偟偰偄傞丅
|
| 幙栤俇丏壠偱僷僜僐儞偑巊偊傑偡偐丅 |
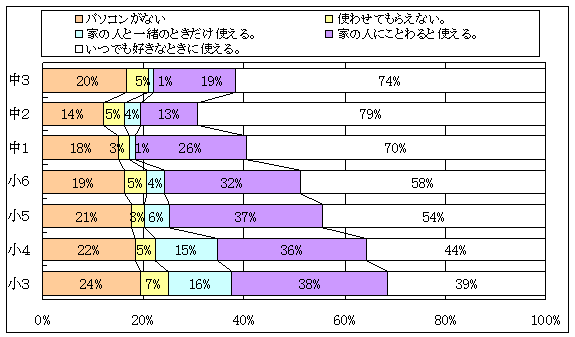 |
 丂俀侽侽係擭搙丂丂 丂俀侽侽係擭搙丂丂 丂俀侽侽俆擭搙丂斾妑 丂俀侽侽俆擭搙丂斾妑 |
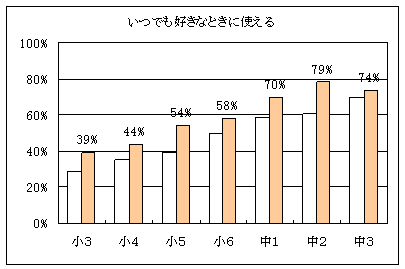 |
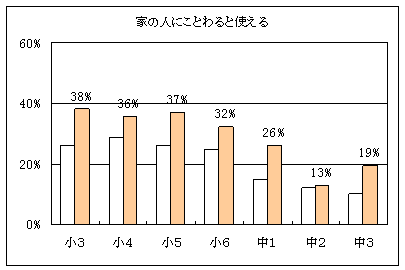 |
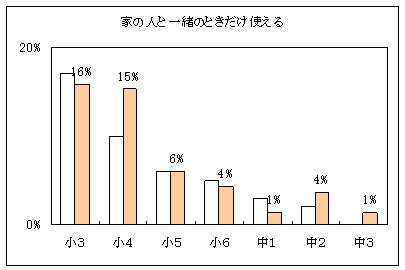 |
|
| 丂彫妛俆擭偐傜斾妑揑帺桼偵巊梡偡傞偙偲偑壜擻偲側偭偰偄傞乮俆侽亾傪墇偊傞乯丅偝傜偵拞妛侾擭偱偼俈侽亾傪墇偊傞丅帣摱惗搆偑堦恖偱僷僜僐儞偵岦偐偆帪娫偑妛擭傪捛偆偵偮傟偰憹壛偟丄壠偺恖偲偄偭偟傚偺巊梡偑彫妛俆擭偱尭彮偟巒傔傞偙偲傕摿挜揑偱偁傞丅 |
|
| 幙栤俈丏帺暘偑帺桼偵巊偊傞実懷揹榖(PHS傪娷傓)傪帩偭偰偄傑偡偐丅 |
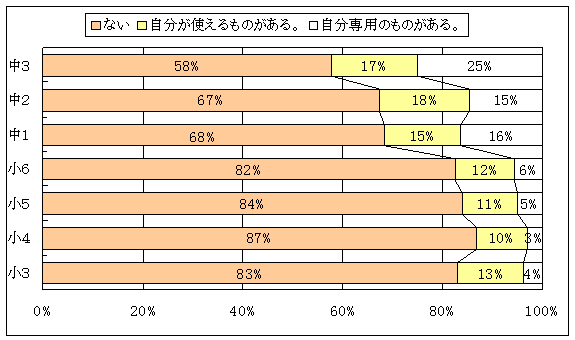 |
 丂俀侽侽係擭搙丂丂 丂俀侽侽係擭搙丂丂 丂俀侽侽俆擭搙丂斾妑 丂俀侽侽俆擭搙丂斾妑 |
|
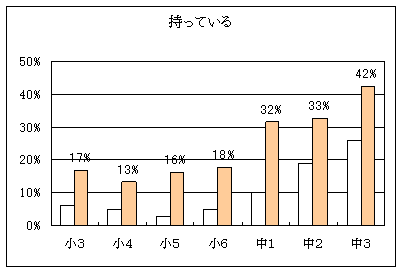 |
|
| 丂帺暘愱梡偺強帩棪偑拞妛侾擭傪嫬偵攞憹偟丄摿偵拞妛俁擭偱偼慡懱偺係妱偑帺暘偺傕偺傪強帩偟偰偄傞丅拞妛擖妛傪婡偵峑撪奜栤傢偢偵妶摦斖埻偑峀偑傝丄強帩偡傞乮壠偺恖偵帩偨偣傜傟傞乯偙偲偑憹偊偼偠傔傞傛偆偱偁傞丅 |
|
| 幙栤俉丏偁側偨偺壠偼丄僀儞僞乕僱僢僩偵偮側偑偭偰偄傑偡偐丅 |
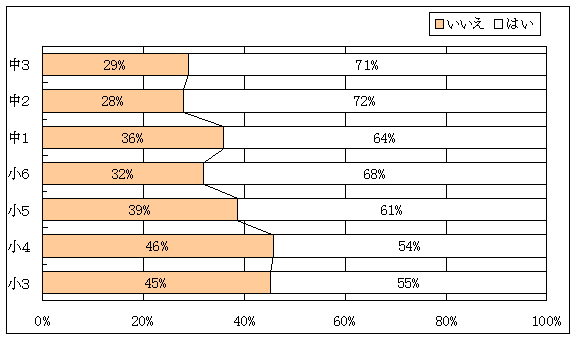 |
| 丂帣摱惗搆戭偺僀儞僞乕僱僢僩晛媦棪偼俆侽亾傪偡傋偰墇偊偰偄傞丅偙偺幙栤偵偮偄偰嶐擭搙偲偺斾妑偼偱偒側偄偑,僀儞僞乕僱僢僩偵愙懕偟偰偄傞壠掚偑崱屻傕憹壛偟偰偄偔偲峫偊傜傟傞丅 |
|
| 幙栤俋丏偁側偨偼壠偱丄僀儞僞乕僱僢僩傪巊偆偙偲偑偱偒傑偡偐丅 |
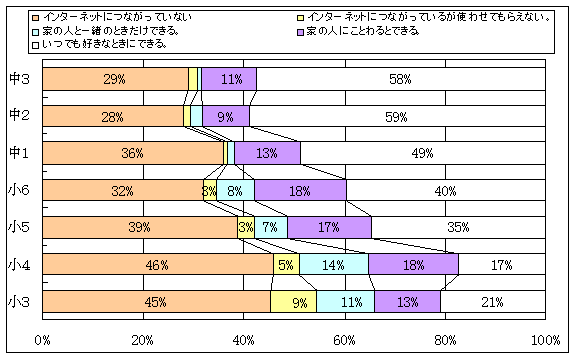 |
 丂俀侽侽係擭搙丂丂 丂俀侽侽係擭搙丂丂 丂俀侽侽俆擭搙丂斾妑 丂俀侽侽俆擭搙丂斾妑 |
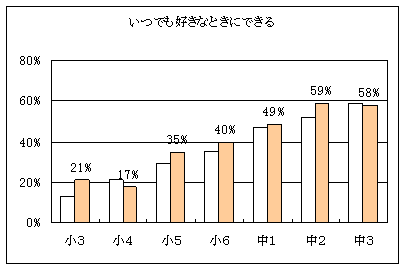 |
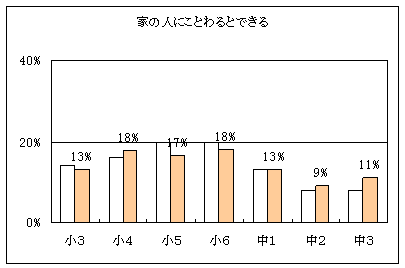 |
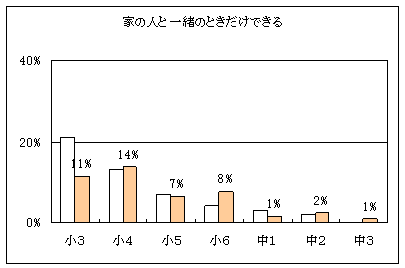 |
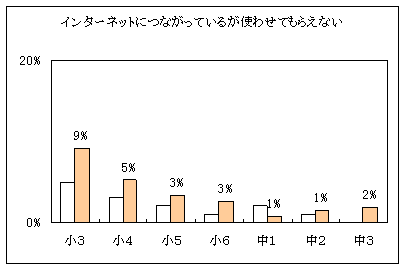 |
| 丂堦恖偱僀儞僞乕僱僢僩傪峴偆帪婜偑嶐擭搙彫妛俇擭偱俆侽亾傪墇偊偨偺偵懳偟偰崱擭搙偼彫妛俆擭偱俆侽亾傪墇偊傞丅壠懓偑晅偒揧傢偢偵堦恖偱僷僜僐儞偵岦偐偆帣摱惗搆偺掅擭楊壔偑恑傒偮偮偁傞丅堦恖偱偄偮偱傕僀儞僞乕僱僢僩傪棙梡偱偒傞帣摱惗搆偼拞妛侾擭偱俆侽亾傪墇偊傞丅 |
|
| 幙栤侾侽丏壠偱僀儞僞乕僱僢僩傪偳偺偔傜偄巊偭偰偄傑偡偐丅 |
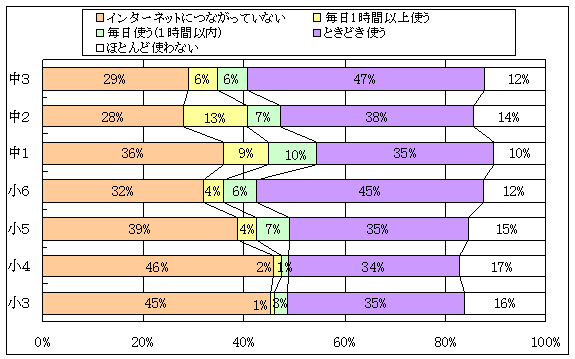 |
 丂俀侽侽係擭搙丂丂 丂俀侽侽係擭搙丂丂 丂俀侽侽俆擭搙丂斾妑 丂俀侽侽俆擭搙丂斾妑 |
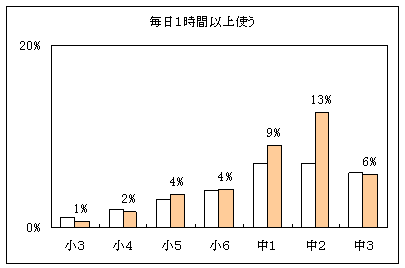 |
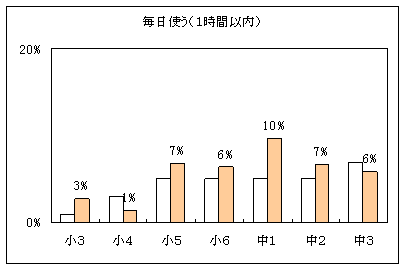 |
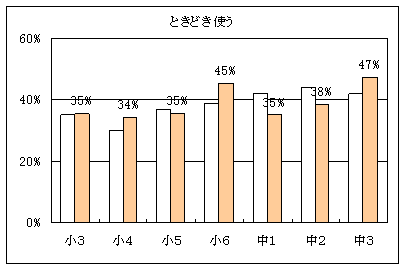 |
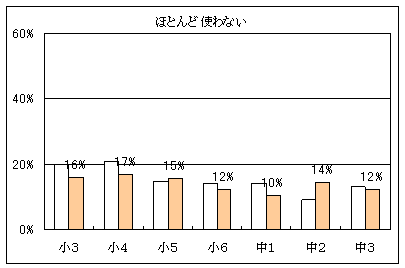 |
| 丂枅擔侾帪娫埲忋僀儞僞乕僱僢僩傪棙梡偡傞挿帪娫巊梡偵偮偄偰偼拞妛侾擭偐傜偦偺孹岦偑傒傜傟傞傛偆偵偁傞丅偨偩偟丄庴尡曌嫮摍偺塭嬁偐拞妛俁擭偱尭彮偡傞丅嶐擭偲斾妑偡傞偲彫妛峑偱偼曄壔偼側偄偑拞妛偱偺挿帪娫巊梡偑嶐擭俇乣俈亾偱偁傞偙偲偲斾傋憹壛偟偰偄傞偙偲偑尒庴偗傜傟傞丅 |
|
幙栤侾侾丏壠偱僀儞僞乕僱僢僩傪偡傞偲偒偵丄壠偺恖偲偺栺懇帠傪寛傔偰偄傑偡偐丅丂丂 丂俀侽侽係擭搙丂丂 丂俀侽侽係擭搙丂丂 丂俀侽侽俆擭搙 丂俀侽侽俆擭搙 |
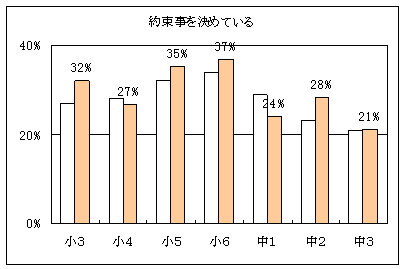 |
|
| 丂彫拞偺暿丄妛擭傪栤傢偢壠掚偱恊偲偺栺懇帠傪寛傔偰僀儞僞乕僱僢僩傪峴偭偰偄傞偺偼慡懱偺偍傛偦俁侽亾偱偁傞丅嶐擭搙偲斾妑偟偰傕傎傏摨條偺夞摎偱偁傝丄曐岇幰偺堄幆偵戝偒側曄壔偼傒傜傟側偄丅偨偩丄彫妛俁擭偱俀俈亾偐傜俁俀亾偵憹壛偟偰偄傞偺偼嶐崱偺僀儞僞乕僱僢僩娭楢偺彅帠忣偵晀姶偵側偭偰偄傞庒偄擭戙偺曐岇幰偺堄幆偺曄壔偺堦偮偐偲巚傢傟傞丅 |
|
幙栤侾俀丏壠偺僷僜僐儞傗実懷揹榖傪巊偭偰丄僀儞僞乕僱僢僩偱尒偨偙偲傗棙梡偟偨偙偲偑偁傞傕偺傪偡傋偰慖傃傑偟傚偆丅
(暋悢夞摎偁傝) |
 丂堦恖偱尒偨傝棙梡偟偨偙偲偑偁傞丂丂 丂堦恖偱尒偨傝棙梡偟偨偙偲偑偁傞丂丂 丂丂壠偺恖偲堦弿偵尒偨傝棙梡偟偨偙偲偑偁傞 丂丂壠偺恖偲堦弿偵尒偨傝棙梡偟偨偙偲偑偁傞 |
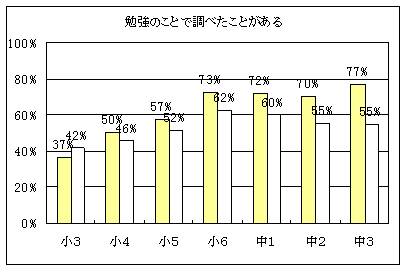 |
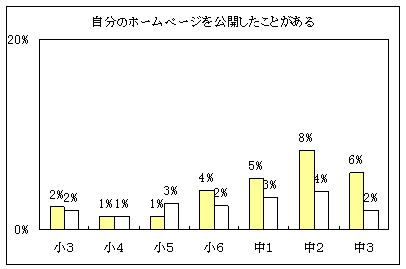 |
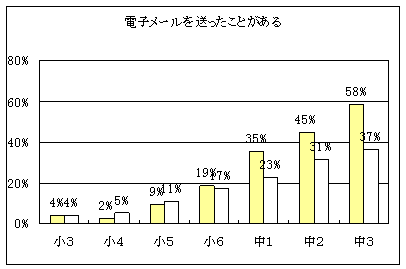 |
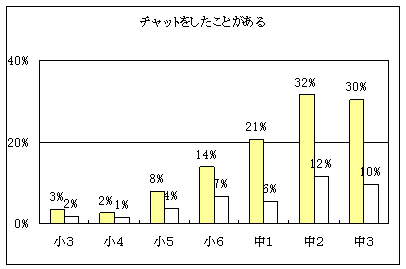 |
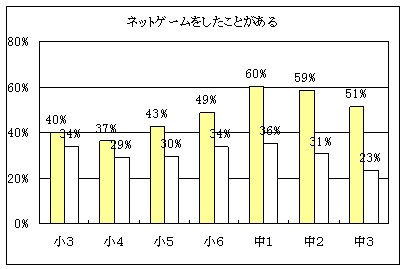 |
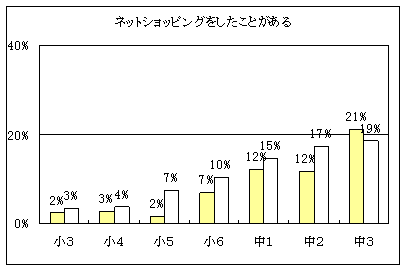 |
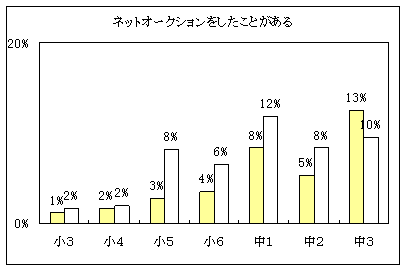 |
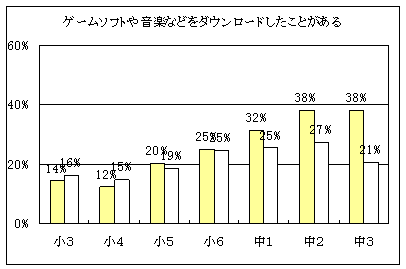 |
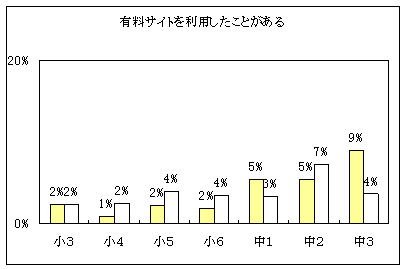 |
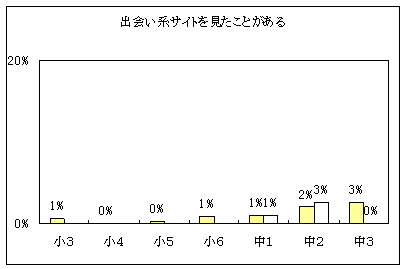 |
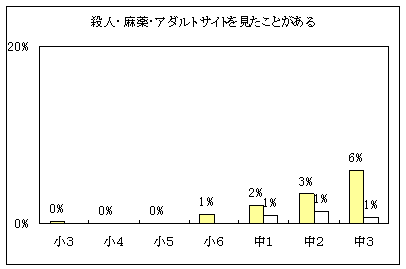 |
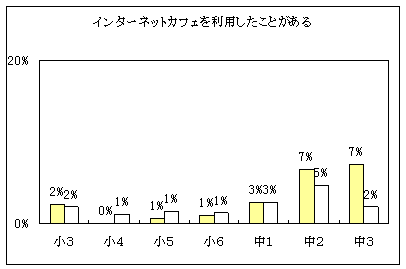 |
丂壠掚偵偍偄偰妛廗偺偨傔偵僀儞僞乕僱僢僩傪棙梡偡傞婡夛偼丄嶐擭搙偵斾傋俈乣侾係亾憹壛偟偰偄傞丅彫妛係擭偱俆侽亾偵払偟偰偄傞偙偲偐傜丄妛廗偵栶棫偮忣曬傪摼傞庤抜偲偟偰偺僀儞僞乕僱僢僩棙梡偑傑偡傑偡怹摟偟偰偒偰偄傞偙偲偑暘偐傞丅
丂僠儍僢僩偺宱尡偼彫妛俆擭偐傜憹偊巒傔丄拞妛俀擭丄拞妛俁擭偱媫憹偡傞丅摿偵拞妛惗偼丄嶐擭搙偵斾傋偰俁乣侾侾亾偺憹壛偱偁傞丅
僱僢僩僎乕儉丄僱僢僩僔儑僢僺儞僌丄僱僢僩僆乕僋僔儑儞傪宱尡偟偨帣摱惗搆傕丄擭乆憹壛偺孹岦偑傒傜傟傞丅
丂偙偺偙偲偐傜丄巹揑側妝偟傒傗曋棙側惗妶偺偨傔偵僀儞僞乕僱僢僩傪棙梡偟巒傔偰偄傞帣摱惗搆偑彊乆偵憹偊偰偄傞偙偲偑暘偐傞丅
弌夛偄宯僒僀僩傗嶦恖丒杻栻丒傾僟儖僩僒僀僩側偳傪墈棗偟偨宱尡偼丄彫妛俇擭偁偨傝偐傜彊乆偵憹偊巒傔偰偄傞偑丄傎傏嶐擭搙暲傒偺妱崌偵棷傑偭偰偄傞丅僀儞僞乕僱僢僩僇僼僃偺棙梡宱尡偼丄慡懱揑偵偼嶐擭搙偲偁傑傝曄傢傜側偄偑丄棙梡宱尡偺偁傞惗搆偑拞妛俀擭埲崀憹偊偰偔傞傛偆偱偁傞丅 |
|
| 亂丂峫丂嶡丂亃 |
丂壠掚偱偺僀儞僞乕僱僢僩棙梡傗僷僜僐儞巊梡偼丄彫妛俆擭偲拞妛侾擭偺俀偮偺帪婜偵偦偺曄壔乮巊梡昿搙偑憹偊傞丄巊梡帪娫偑憹偊傞丄強帩棪偑憹偊傞側偳乯傪傒傞偙偲偑偱偒偦偆偱偁傞丅
丂傑偨丄拞妛俁擭偱偼庴尡曌嫮偺塭嬁偐傜偐挿帪娫巊梡偼尭彮偡傞傕偺偺丄僀儞僞乕僱僢僩僇僼僃偺棙梡傗実懷揹榖乮俹俫俽乯摍偺強帩棪偑憹壛偟偰偄傞偙偲偐傜丄帺戭埲奜偺応強偱傕僀儞僞乕僱僢僩傪棙梡偟偰偄傞壜擻惈偑偁傞丅妛擭偑忋偑傞偵偮傟偰丄壠懓偺栚偵怗傟側偄偲偙傠偱忣曬廂廤傗忣曬岎姺傪峴偆偙偲偑懡偔側偭偰偄偔丄偲偄偆孹岦偑悇應偱偒傞丅偟偨偑偭偰丄僀儞僞乕僱僢僩棙梡傗実懷揹榖偺巊梡偵摉偨偭偰偼丄帣摱惗搆偑偦偺婋尟惈傪廫暘偵棟夝偟偨忋偱巊梡偡傞偙偲偑偱偒傞傛偆丄壠掚偺傒側傜偢妛峑嫵堢偺応柺偱傕巜摫偡傞婡夛傪愝偗偰偄偔偙偲偑丄崱屻傑偡傑偡昁梫偵側偭偰偄偔偲峫偊傜傟傞丅 |
|
|
|