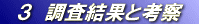 |
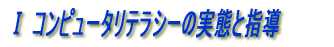 |
| 【設問について】 |
小・中学校の教育用コンピュータの整備がさらに進み,学習活動においてコンピュータが広く使われ,また,家庭での普及も目覚ましい現在,児童・生徒のコンピュータリテラシーの実態を把握し,今後の指導に生かしていくことを目的に,設問を設定した。
尚,児童・生徒に意味がより伝わりやすいように質問の文言は若干修正したが,年度ごとの推移をつかみたいというねらいがあることから,質問の項目は平成15年度から4年間,踏襲している。 |
|
質問4.「できること」を全て選んでください。  2005年度 2005年度  2006年度 2006年度 |
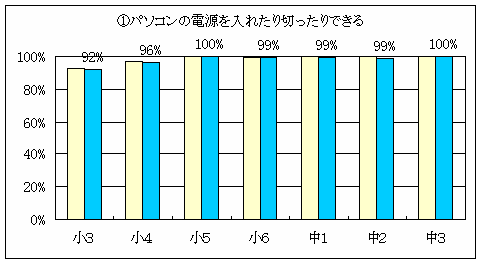 |
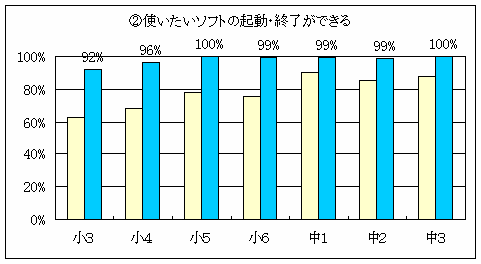 |
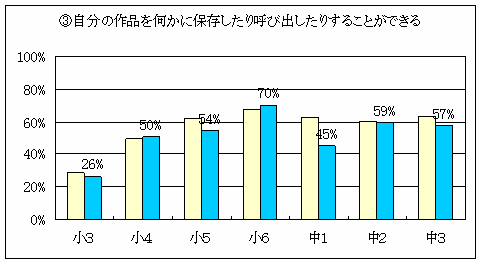 |
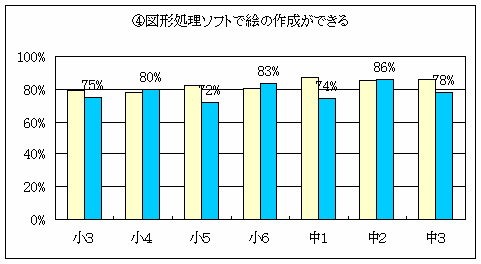 |
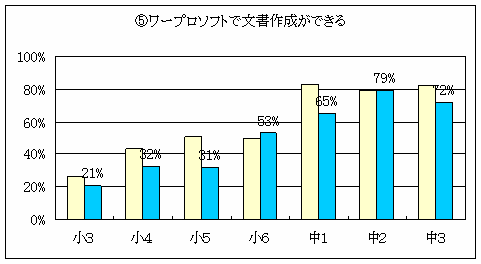 |
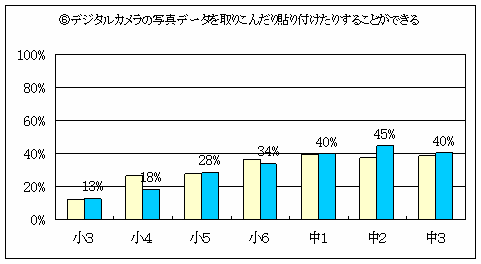 |
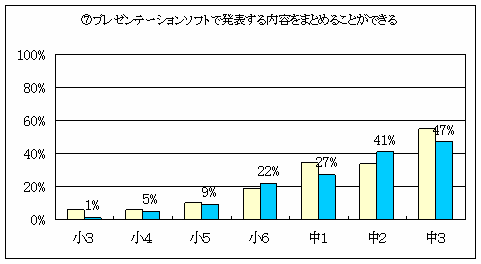 |
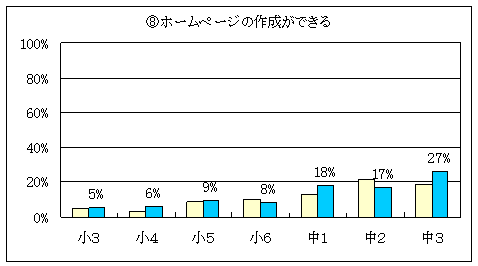 |
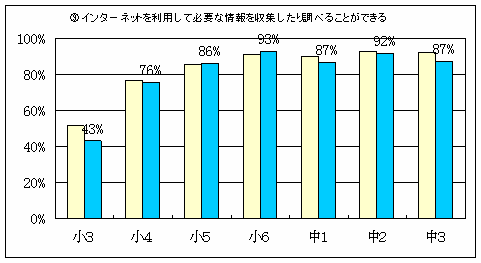 |
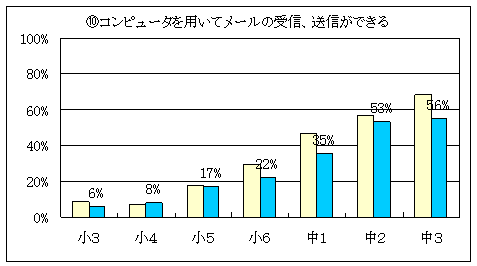 |
|
| 質問5.普段どんな方法で文字入力をしていますか。 |
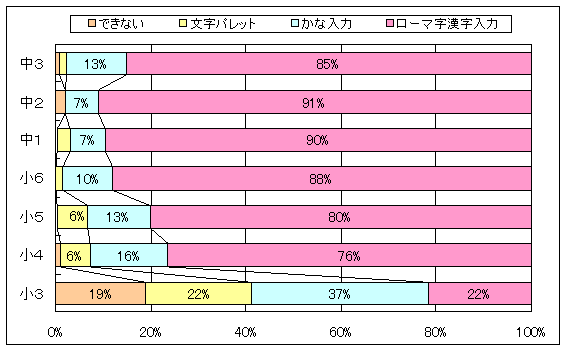 |
|
質問6.使うことのできるものを全て選んでください。  2005年度 2005年度  2006年度 2006年度 |
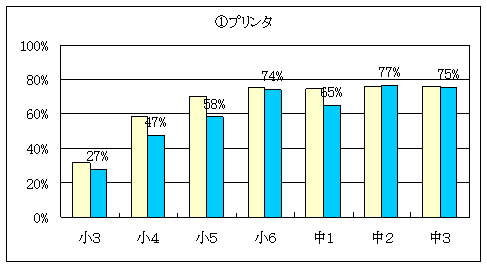 |
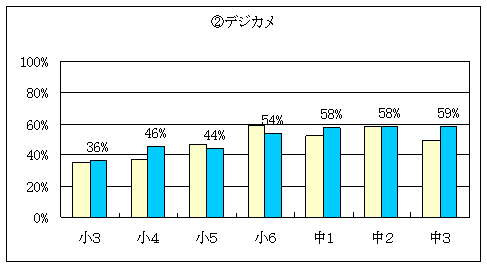 |
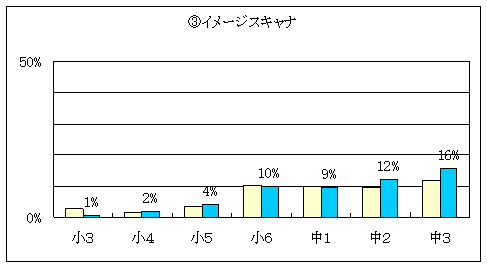 |
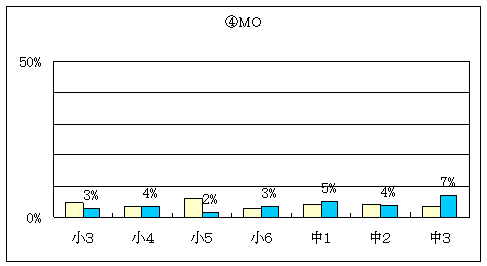 |
|
質問7.授業で学習した内容を全て選んでください。  2005年度 2005年度  2006年度 2006年度 |
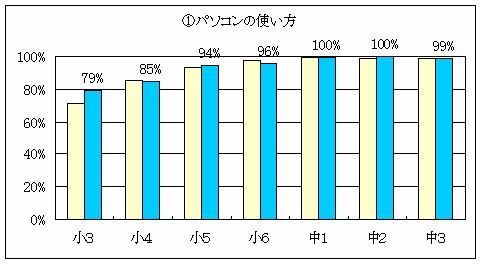 |
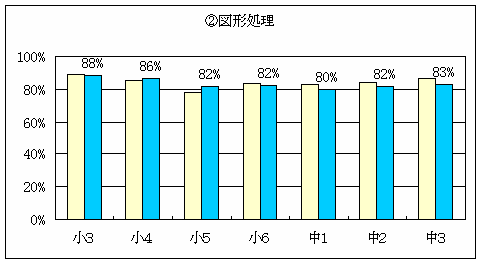 |
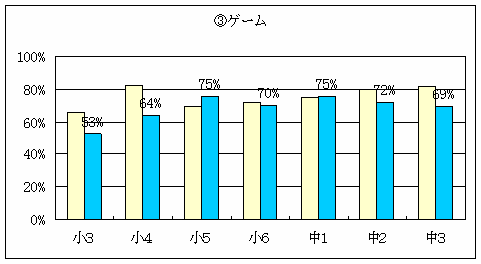 |
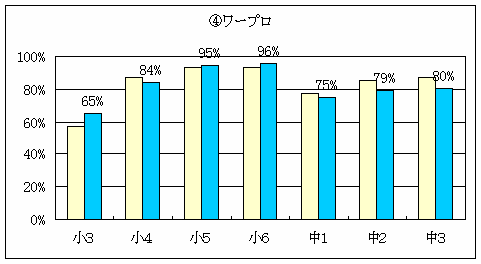 |
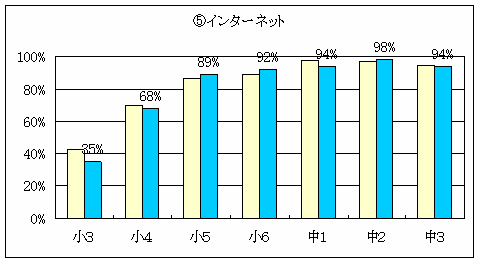 |
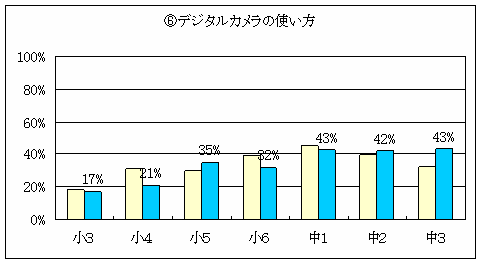 |
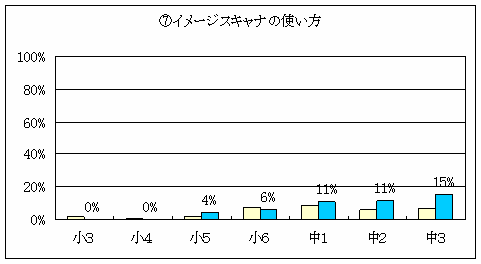 |
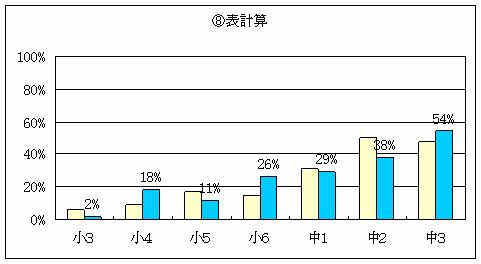 |
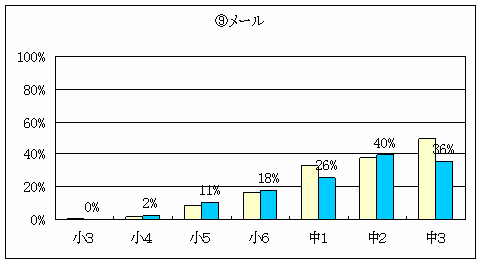 |
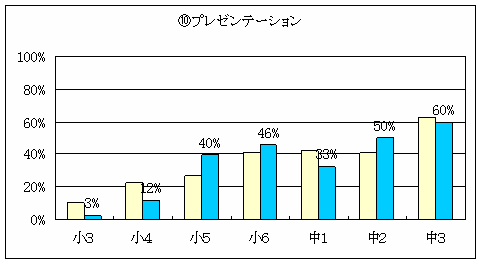 |
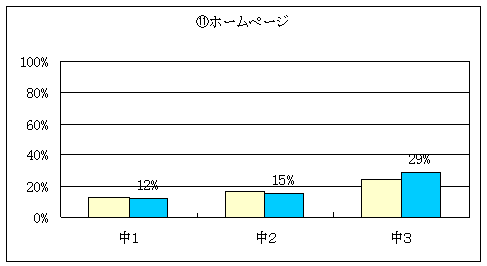 |
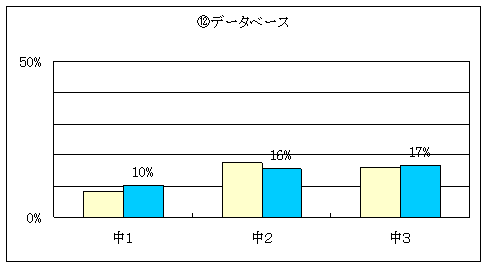 |
|
| 【 考 察 】 |
児童・生徒のリテラシーについては年々向上しているようだが,ここ数年は急激な変化は見られず,一部頭打ちの傾向も見られる。
インターネット利用に関する項目の回答から,学習の中で「情報を収集する手段」としてコンピュータを利用する機会は増えてきたということが言えそうである。一方,「情報を発信する手段」「表現する手段」としてコンピュータを用いることについては,より一層の充実を図っていく余地がある。「ワープロソフトで文書を作成することができる」と答えた小学生が昨年度よりも減少したことや,小・中ともに学習の中でプレゼンテーションソフトやメールの送受信などを経験している児童・生徒の割合がなかなか伸びないという実態などは,今後各校で学習計画を作成する際の参考になるのではないだろうか。
文字入力のスキルに関しては,中学2年生と3年生の間に逆転の現象が見られる。中学2年生の生徒は,学校支援事業の導入時に小学6年生であったため,小学校の学習の中でサポートの協力を得ながら文字入力の方法を習得したケースも多いのではないかと思われる。
周辺機器の操作については,デジタルカメラやイメージスキャナなど,画像を取り込む機器の操作に関するスキルがわずかながらも向上している。「情報を発信する手段」「表現する手段」としてのコンピュータ利用が充実してくれば,これらの機器の操作に関するスキルも今以上に向上するのではないかと思われる。
「プリンタを使うことができる」と答えた小学生は昨年より少ないが,これは,プリンタの扱い(機器の選択・用紙設定・紙詰まりやインクのトラブルなどへの対処)の難しさや印刷にかかるコスト等との関連もあるのではないだろうか。
コミュニケーションシステムの共有キャビネットには,各校の情報教育年間計画や詳細な指導計画が保管されており,いつでも閲覧できるようになっている。他校の計画や実践も参考にしながら,それぞれの学校の児童・生徒に必要なリテラシーを整理して,計画的に身に付けさせていく取り組みが望まれる。 |
|
|
|