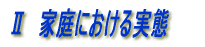 |
| 亂愝栤偵偮偄偰亃 |
|
| 幙栤俉丏壠偵僷僜僐儞偑偁傝傑偡偐丅 |
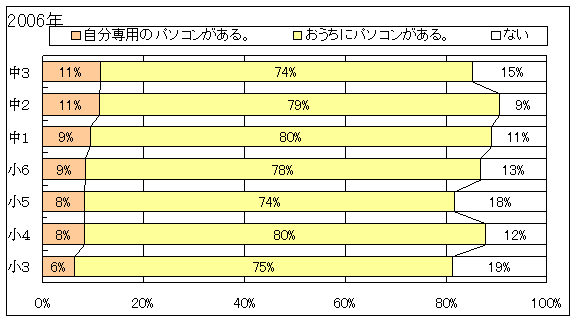 |
|
| 幙栤俋丏壠偱僷僜僐儞偑巊偊傑偡偐丅 |
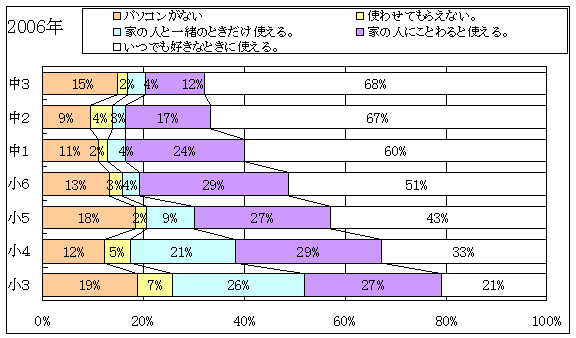 |
 丂俀侽侽俆擭搙丂丂 丂俀侽侽俆擭搙丂丂 丂俀侽侽俇擭搙丂斾妑 丂俀侽侽俇擭搙丂斾妑 |
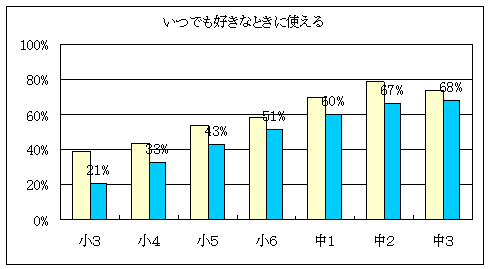 |
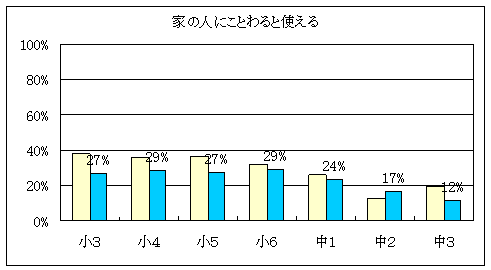 |
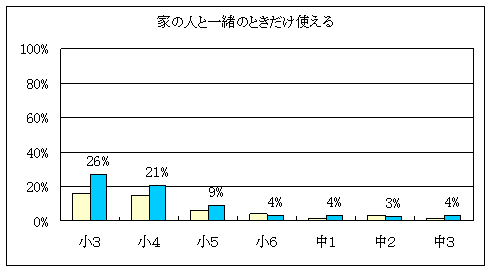 |
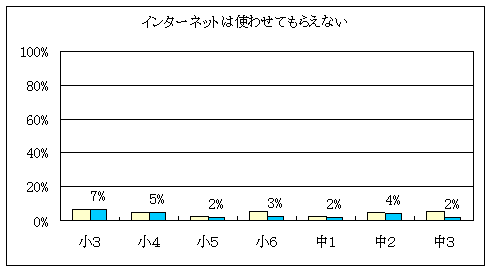 |
|
| 幙栤侾侽丏帺暘偑帺桼偵巊偊傞実懷揹榖(PHS傪娷傓)傪帩偭偰偄傑偡偐丅 |
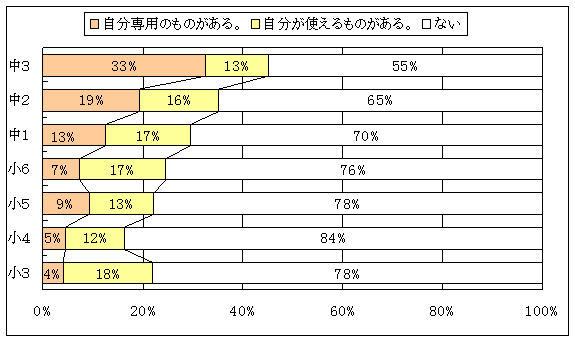 |
 丂俀侽侽俆擭搙丂丂 丂俀侽侽俆擭搙丂丂 丂俀侽侽俇擭搙丂斾妑 丂俀侽侽俇擭搙丂斾妑 |
|
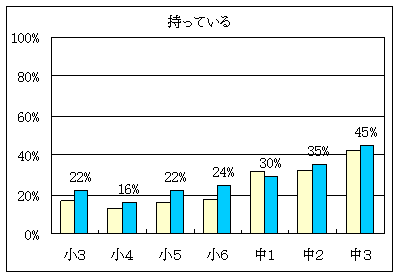 |
|
|
| 幙栤侾侾丏偁側偨偺壠偼丆僀儞僞乕僱僢僩偵偮側偑偭偰偄傑偡偐丅 |
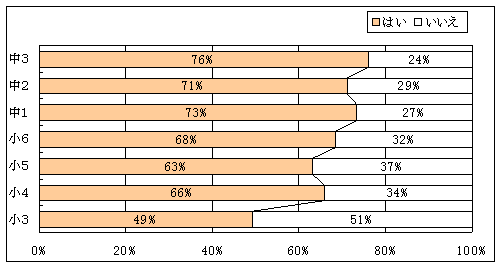 |
|
| 幙栤侾俀丏偁側偨偼壠偱丆僀儞僞乕僱僢僩傪巊偆偙偲偑偱偒傑偡偐丅 |
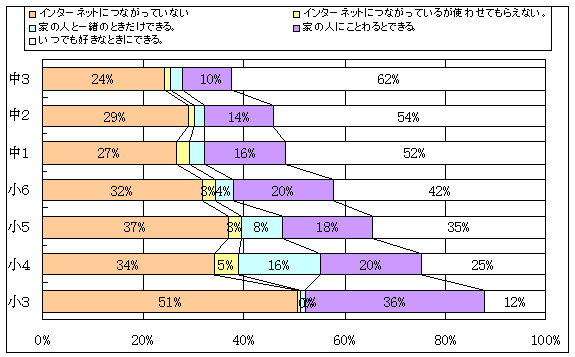 |
 丂俀侽侽俆擭搙丂丂 丂俀侽侽俆擭搙丂丂 丂俀侽侽俇擭搙丂斾妑 丂俀侽侽俇擭搙丂斾妑 |
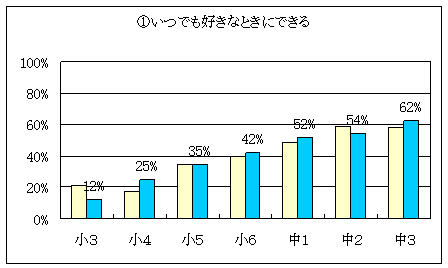 |
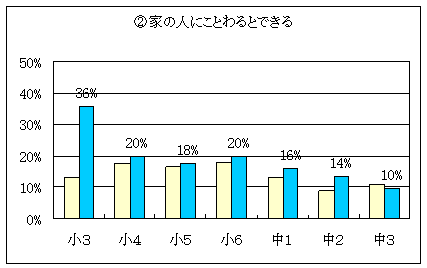 |
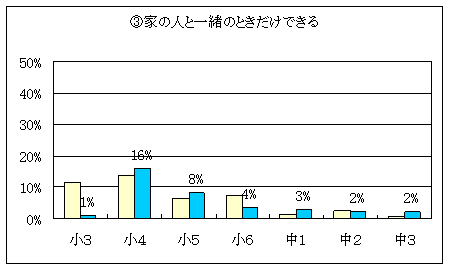 |
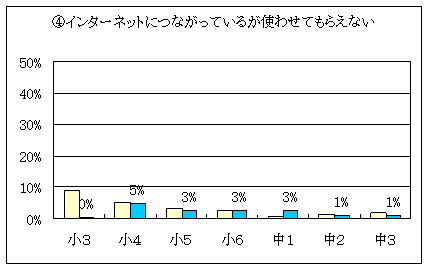 |
|
| 幙栤侾俁丏壠偱僀儞僞乕僱僢僩傪偳偺偔傜偄巊偭偰偄傑偡偐丅 |
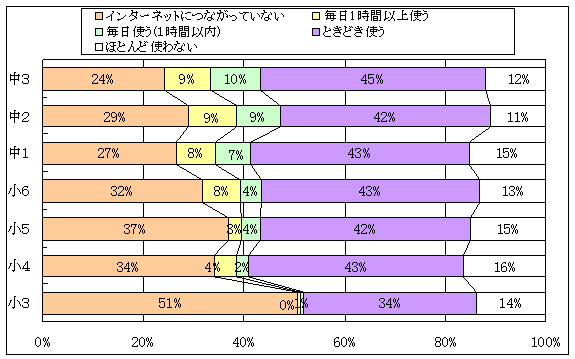 |
 丂俀侽侽俆擭搙丂丂 丂俀侽侽俆擭搙丂丂 丂俀侽侽俇擭搙丂斾妑 丂俀侽侽俇擭搙丂斾妑 |
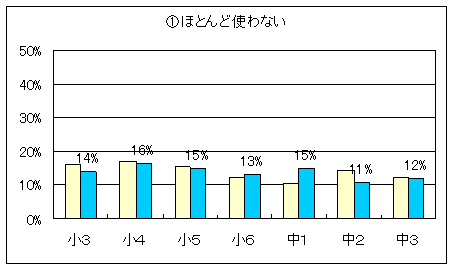 |
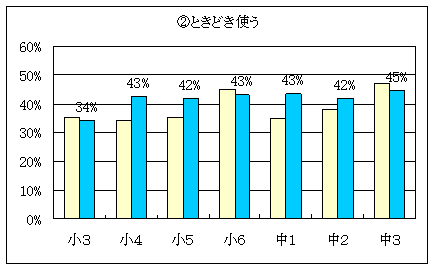 |
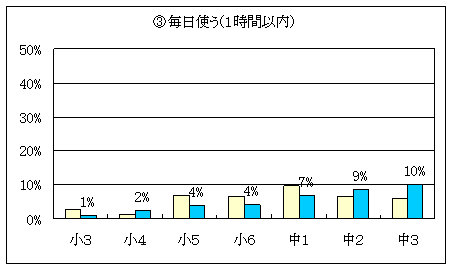 |
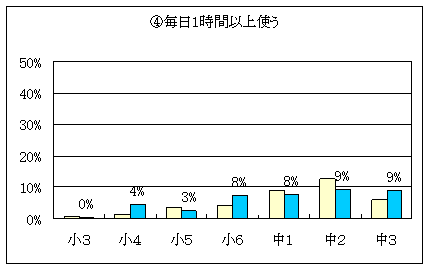 |
|
幙栤侾係丏壠偱僀儞僞乕僱僢僩傪偡傞偲偒偵丆壠偺恖偲偺栺懇帠傪寛傔偰偄傑偡偐丅丂丂 丂俀侽侽俆擭搙丂丂 丂俀侽侽俆擭搙丂丂 丂俀侽侽俇擭搙 丂俀侽侽俇擭搙 |
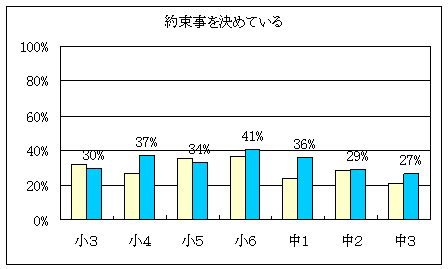 |
|
|
幙栤侾俆丏壠偺僷僜僐儞傗実懷揹榖傪巊偭偰丆僀儞僞乕僱僢僩偱尒偨偙偲傗棙梡偟偨偙偲偑偁傞傕偺傪偡傋偰慖傃傑偟傚偆丅
(暋悢夞摎偁傝) |
 丂堦恖偱尒偨傝棙梡偟偨偙偲偑偁傞丂丂 丂堦恖偱尒偨傝棙梡偟偨偙偲偑偁傞丂丂 丂丂壠偺恖偲堦弿偵尒偨傝棙梡偟偨偙偲偑偁傞 丂丂壠偺恖偲堦弿偵尒偨傝棙梡偟偨偙偲偑偁傞 |
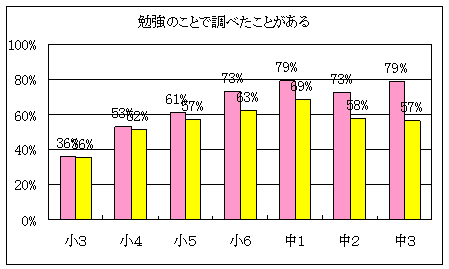 |
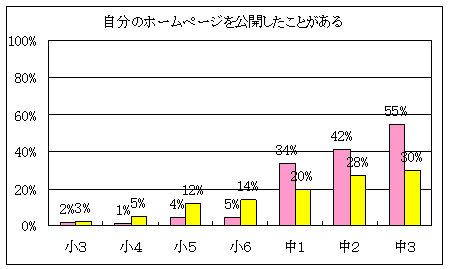 |
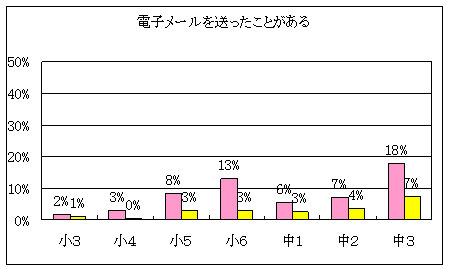 |
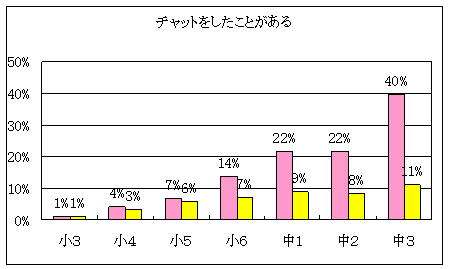 |
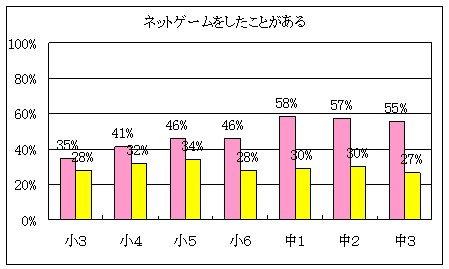 |
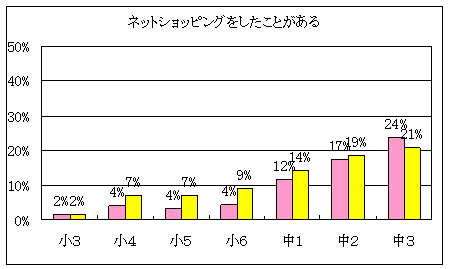 |
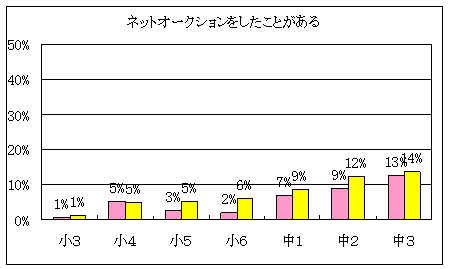 |
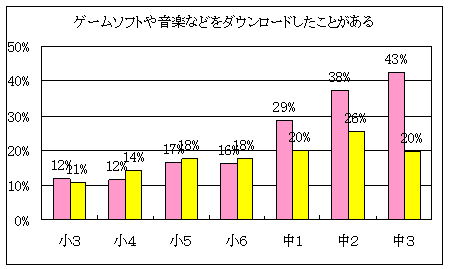 |
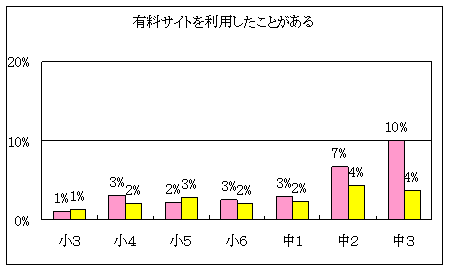 |
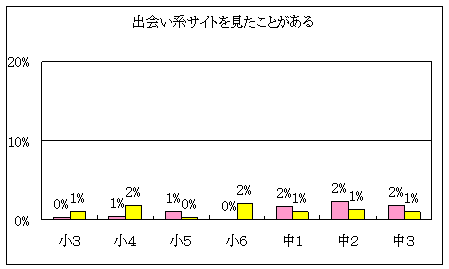 |
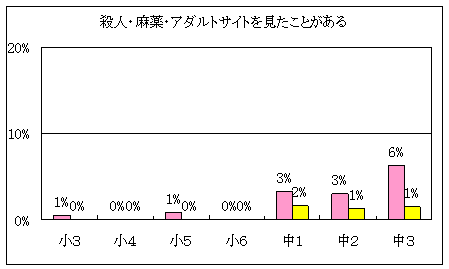 |
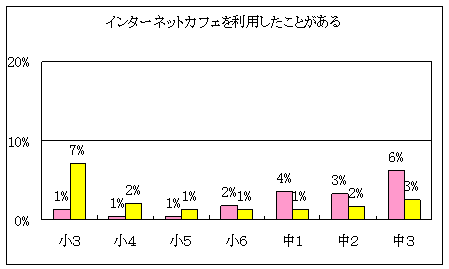 |
|
| 亂丂峫丂嶡丂亃 |
丂壠掚偱恊偲偺栺懇帠傪寛傔偰僀儞僞乕僱僢僩傪棙梡偟偰偄傞帣摱丒惗搆偺妱崌偑丆傢偢偐偱偼偁傞偑憹壛偟偰偒偰偄傞丅偙偺寢壥偼丆曐岇幰偺堄幆偺曄壔偺昞傟偲傕撉傒庢傞偙偲偑偱偒傞丅偟偐偟丆帣摱丒惗搆偑妛廗埲奜偺巹揑側妝偟傒傗惗妶偵栶棫偰傞栚揑偱僀儞僞乕僱僢僩傪棙梡偡傞婡夛偼擭乆憹偊偰偒偰偄傞偨傔丆崱屻偼奺壠掚偺敾抐偵擟偣傞偩偗偱偼廫暘偲偼尵偊側偄偩傠偆丅僀儞僞乕僱僢僩偺揔愗側棙梡偺巇曽傗僱僢僩幮夛偵愽傓婋尟惈偺棟夝丆挊嶌尃摍偵懳偡傞擣幆側偳偵偮偄偰偼丆妛峑偱傕廫暘巜摫偟丆壠掚偵傕孾栔傪懀偟偰偄偔偙偲偑昁梫偵側偭偰偄偔偲峫偊傜傟傞丅
丂実懷揹榖偺強帩棪偑丆傎偲傫偳偺妛擭偵偍偄偰憹壛偟偰偄傞丅偙偺挷嵏偱偼乽捠榖乿乽儊乕儖乿乽僀儞僞乕僱僢僩棙梡乿側偳偺梡搑偵偮偄偰徻偟偄暘愅偼偱偒側偄偑丆実懷揹榖傪梡偄偰忣曬傪摼偨傝屳偄偵忣曬傪岎姺偟偨傝偡傞偲偄偆峴堊偑丆帣摱丒惗搆偵偲偭偰傛傝恎嬤側傕偺偵側偭偰偒偨偲偄偆偙偲偼尵偊偦偆偱偁傞丅慡崙揑偵丆帣摱惗搆偑実懷揹榖偺僒僀僩傪棙梡偟偰偄偰斊嵾傗僩儔僽儖偵姫偒崬傑傟傞偲偄偆働乕僗偑屻傪愨偨側偄丅実懷揹榖傕僐儞僺儏乕僞偲摨條丆恎嬤側忣曬僣乕儖偺堦偮偵側偭偰偒偰偄傞偲偄偆偙偲傪擣幆偟偨忋偱偺巜摫偑昁梫偱偁傞丅丂丂丂丂 |
|
|
|