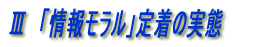 |
| 【設問について】 |
| 学校の授業でもコンピュータが日常的に活用されている中、児童・生徒の情報モラルについての定着状況を把握すると共に、今後指導が必要とされる事項について確認し今後の指導の参考にするため、以下の設問を設けた。加えて、今年度からは昨今の社会情勢を踏まえ、インターネットの掲示板に関する項目を新たに設定した。 |
|
| 質問13.自分の他に友だちも写っている写真をホームページに出す時、気をつけなければならないことは何でしょうか。 |
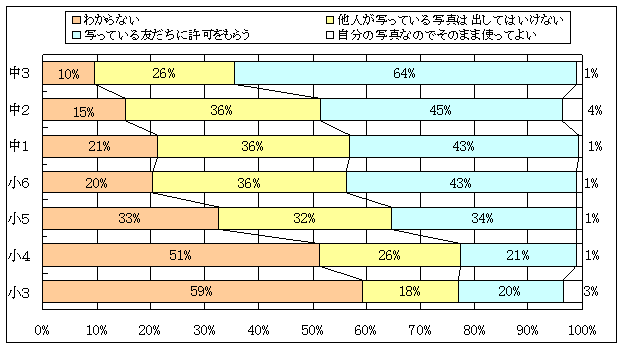 |
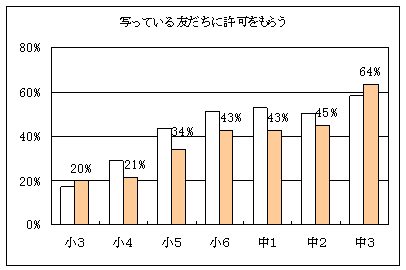  2004年度 2004年度  2005年度 2005年度 |
|
| 各学年の1割以上の子ども達は、自分の写真ということでそのまま掲載してよいと考えている。各学校でデジタルカメラを使う時の事前指導の際に、写真をとるときのルールを指導する必要がある。相手の許可をとることや、個人が特定できないようにすること等を、学年に応じて指導していかなければならない。学年が進むにつれて友だちに許可をもらう児童生徒が増えていることは、肖像権についての理解が深まっていると考えられる。 |
|
| 質問14.他人のホームページにのっている詩や写真を自分のホームページに載せる時、気をつけなければならないことは何でしょう。 |
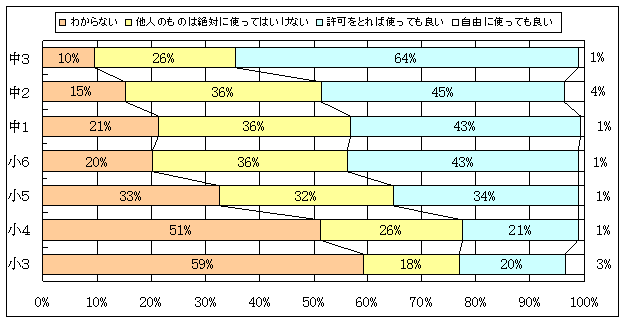 |
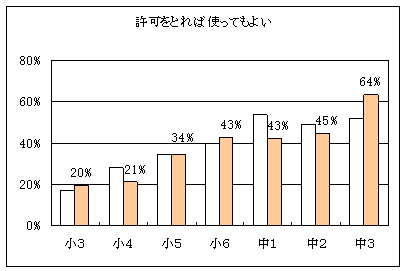   2004年度 2004年度   2005年度 2005年度 |
|
| 質問13同様、学年が進むにつれ、他人のホームページの詩や写真を使用する時は、許可をとってから使うと答えている児童生徒が増えている。また、小3~小4年では、わからないと答えている子どもが過半数を占めていることから、写真などを活用する機機会が少ないことも影響していると思われる。この実態を踏まえながら、文章や画像を無断でコピーしたり、使ったりしないことを理解させ、「著作権」を大切にする心を育てていく必要がある。また、今後は一般的な「著作権」と合わせて、効果的に指導していくことが望ましい。 |
|
| 質問15.インターネットで調べているうちに、変な写真が掲載されているページが現れました。あなたはどうしますか。 |
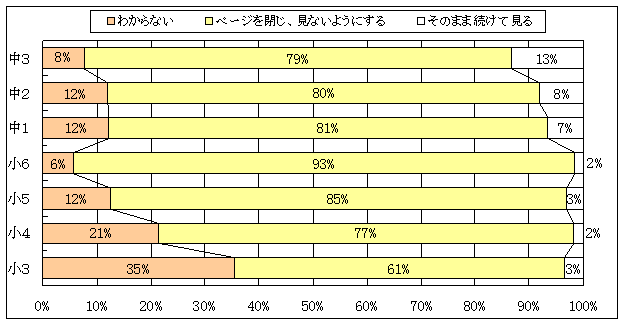 |
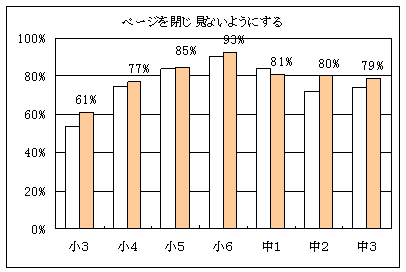  2004年度 2004年度  2005年度 2005年度 |
|
| すべての学年でページを見ないようにするが6割以上をを占めており、有害情報に関する指導の成果が表れてきていると考える。ただし、中1以上では、そのまま見続けるが学年を追うに連れて増加傾向にある実態を踏まえ、生徒指導ばかりでなく様々な場面をとらえて、「有害情報」に関する正しい理解と対処の仕方を指導しなければならない。一方で、今後は、生徒指導とも連携を図りながら有害情報に関する系統だった指導計画の見直しがより一層求められる。また、文章や考え方に関する指導内容も考慮していく必要がある。 |
|
| 質問16.家に「24時間以内に、5人この電子メールを出さないと、あなたは不幸になる。このメールをすぐに出しなさい。」というメールが届きました。あなたはどうしますか。 |
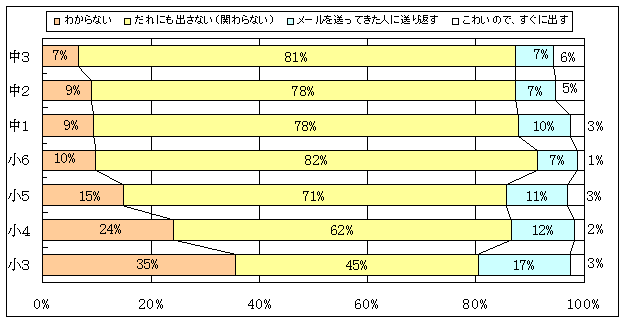 |
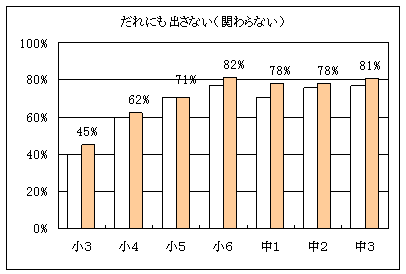  2004年度 2004年度  2005年度 2005年度 |
|
| メール交換の機会が増える中1以上の学年では、7割以上がだれにも出さないを占めている一方で、3%の生徒がすぐ出すと回答していることは、直接的間接的に迷惑メールに関する経験や情報に接していることが要因と思われる。被害者にならないだけでなく、加害者にもならないようにする指導として、インターネットの向こうには同じ人間がいることを意識させることが求められる。相手の立場に立って考えることや、お互いに相手を思いやる気持ちをもつことなどについて、小中を問わず迷惑メールへの対処方法について正しい認識をもつための指導をしていく必要がある。 |
|
| 質問17.インターネット上で知り合った人に、伝えて良いあなたの情報はどれでしょうか。すべて選んでください。(複数回答可) |
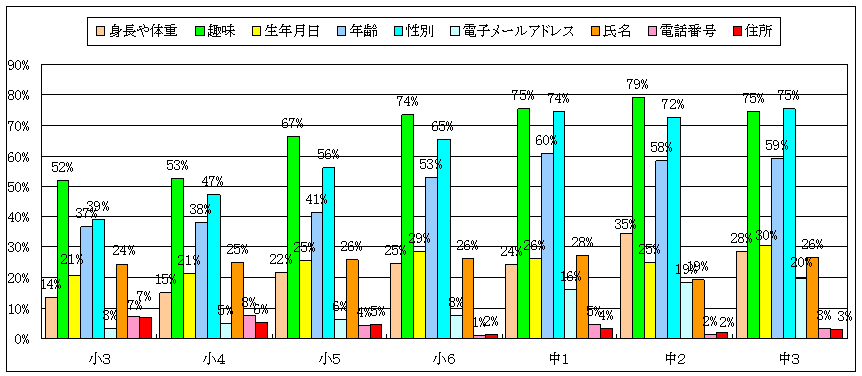 |
| どの学年も「趣味」「性別」「年齢」を伝えても良いことが上位を占め、インターネット上で知り合った人と個人を特定させずにコミュニケーションの伝達方法を知っていることが考えられる。「電子メールアドレス」については学年が上がるにつれて伝えても良いと考える割合が増えている。中学生になり、パソコンや携帯で実際にメール交換を行う生徒が増えることが要因と考えられる。見知らぬ人に気軽にメールアドレスを教えてはいけない事を知らせていく必要がある。また、個人情報を守るという点で、住所、電話番号、生年月日、身体的特徴(身長・体重)などの情報は公開してはいけないことを今後も徹底していかなければならないと共に、必要に応じて「個人情報」を教える際には、家の人と相談するなど慎重に対応することを加えて指導しておく必要がある。 |
|
| 質問18.学校でインターネットを見ている時に、学習に役立ちそうなプログラムソフトを見つけました。あなたはどうしますか。 |
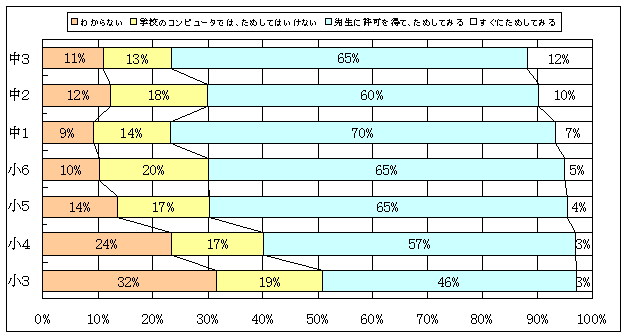 |
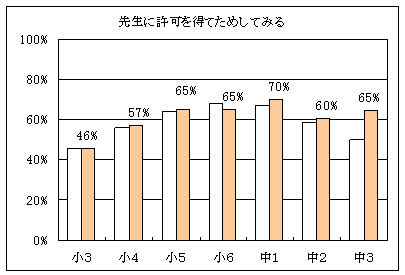  2004年度 2004年度  2005年度 2005年度 |
|
| コンピュータやインターネットに興味や関心が高まる中1頃からは、自宅でゲームプログラム等をダウンロードして使う経験をもつ生徒は少なくない。公共物である学校のコンピュータで、プログラムをダウンロードし使用することは原則禁止されている。学年に応じて指導していくべきである。しかし、ダウンロードをしなければならない状況を想定した約束を児童生徒に教えたり、教師に相談する信頼関係を構築したりしておくことが必要である。 |
|
| 質問19.学校でインターネットをしているうちに、急にうずまき模様が画面に表れるようになりました。あたなはどうしますか。 |
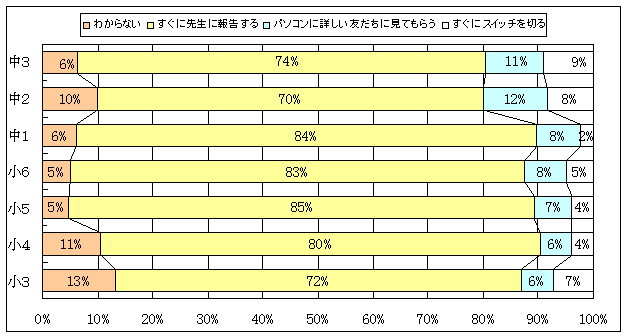 |
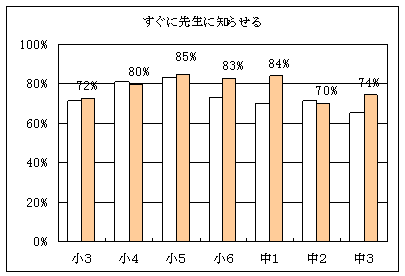  2004年度 2004年度  2005年度 2005年度 |
|
| 各学年で約7割以上が先生に報告するとしており、事態の重大さを深刻に受け止めていることがうかがえる。異常に気づいた時はいち早く先生に知らせることを児童生徒に徹底しておくことが大切である。また、実社会ではすでにウィルス対策が必要不可欠になっている事を重視し、ウィルス被害の深刻さやウィルス対策の重要性について、シミュレーションソフトなどを用いて、具体的な事例をもとに学年に応じた指導を実施する必要がある。 |
|
| 質問20.コンピュータのパスワードを管理するためには、どうすればよいでしょうか。 |
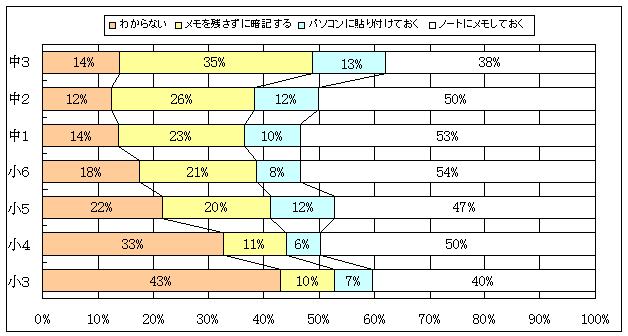 |
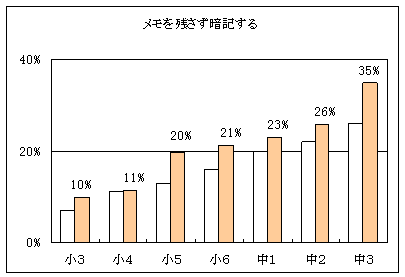  2004年度 2004年度  2005年度 2005年度 |
|
| パスワードを「メモをする」「貼り付ける」とした子どもを合わせると、ほとんどの学年で半数にも上っている。このことは、経験が少ないことや必要性を感じる場面が少ないことが要因と考えらる。また、反対に暗記する子どもはどの学年でも昨年度より増加している。現状では子どもにとってあまり馴染みのないパスワードではあるが、最近の事件報道などによりその重要に意識している児童生徒は少なくない。このことから、今後具体的な事例をもとに学年に応じた指導を計画的に実施する必要があると考える。 |
|
| 質問21.インターネットで買い物をする時に大切なことはなんでしょうか。 |
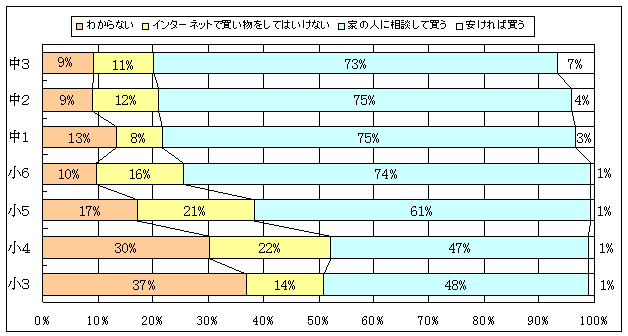 |
|
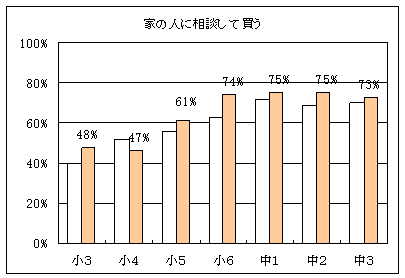  2004年度 2004年度  2005年度 2005年度
|
|
| 昨年度に比べ、小学校高学年以上で「家の人と相談して買う」の割合が増えてきており、情報モラル教育の成果が出ていると考えられる。一般的にインターネットショッピングやオークションでは、家にいながら気軽に、一般価格よりも安価で商品を購入する事ができる為、利用者は増えてきている。小中学生には、その利点だけでなく起こりうる危険性(ネット詐欺)なども仮想体験させながら分かりやすく教えていく必要があり、インターネットで買い物をする時には家族と一緒に、相手先が信用できるのかを確かめながら進めることが合わせて指導したい。。また、また将来のことを考えてクレジットカードの使い方などにもふれ、個人情報が漏れないように細心の注意を払い、児童生徒が勝手に使用することのないよう留意したい。 |
|
| 質問22.インターネットの掲示板に、自分の自慢話を書いたら、そのことについて悪口を書かれてしまいました。あなたはどうしますか? |
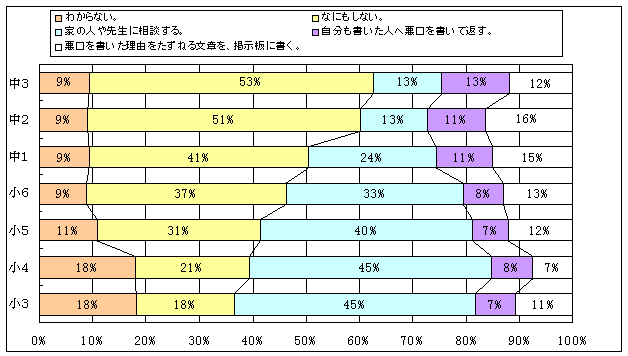 |
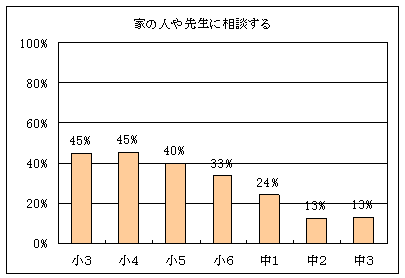  2005年度 2005年度 |
|
| 学年が進むに連れて、「家の人や先生に相談する」の割合が減少し、反対に「何もしない」の割合が顕著に増加している傾向が見られる。誰にも相談せずに一人で悩みを抱え込んでしまうことも考えられるので、相手から挑発的な書き込みをされた時は挑発に乗らないように注意すること、さらに自分がひどく傷つけられた場合は、家の人や先生に相談したり、掲示板を管理している人に対処してもらうこと等を、授業の中で実際に仮想掲示板での書き込みを経験させながら指導していくことが重要である。また、不特定多数が利用することの多い掲示板では、自分にはそのつもりがなくても傷つけられると感じる人もいるので、相手の気持ちを考えて書き込むことが求められる。インターネットは日常生活同様相手を傷つけたり、相手が嫌がるようなことを書き込むことは許されないことを教えていく必要がある。 |
|
| 【 考 察 】 |
|
急速な変化を遂げ,年々身近になるネットワーク社会は,確実に利便性が向上し多様化し続けている。全く自由な自己表現・発信の場としてのブログや,小学生にまでも広がりを見せる株のネット取引など,児童生徒を取りまくネットワーク環境は,一方で児童生徒の生活に少なからぬ影を落としている実態がある。こうした環境の変化に伴い,ネットワーク上でトラブルにあう児童生徒が増加する傾向にあり,各校においては,「情報モラル教育」に本格的に取り組む必要が迫っている。学校として情報モラル指導のための計画を整備し,日常のこととして情報モラル指導を学校全体で取り組むことが急務である。
学校として情報モラル教育を推進するためには,教師自らが主体的に情報社会に関与し,日々進歩し変化するITやネットワーク社会の動向を正しく把握することを通して,子ども達に対する情報モラル指導の重要性について再認識することが求められる。その上で,IT環境をよりよく活用し,学習に効果的に活かすための実践力を育てることを基本に,ネットワーク上で身を守る心構えや姿勢,危険を上手に回避するための知識や手段を適切に指導していかなければならない。そのためには,関係機関や専門家との連携も視野に入れながら,より具体的な指導法を研修することが必要である。
しかし一方で,情報モラル育成の課題は,けっして学校だけが取り組むことで解決できる課題ではない。家庭でのIT利用が非常に日常化していることをふまえ,本実態調査の結果などを基に学校と家庭・教師と保護者がともに研修する場を設定し,情報化に伴う諸課題と子どもの実態についての認識を共有することが必要である。その中で,家庭でネットワークや携帯電話などのIT環境を使用する際の約束を早い段階で話し合い,子どもの状況や発達に合わせて内容を見直すことが必要なことを周知し,子どもが安全にIT環境を利用することができる環境づくりに協力してもらうことう重要である。このように学校と家庭が連携することで,何か問題が発生した場合に学校と家庭がすぐに相談・対応できる関係づくりにつながるものと思われる。
9年間の義務教育終了時には,ネットワーク社会に参画するための判断力や自制心ある子どもに育てることが,我々大人の重要な役割である。
|
|
|
|