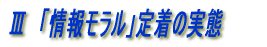 |
| 【設問について】 |
| 学校の授業でもコンピュータが日常的に活用されている中,児童・生徒の情報モラルについての定着状況を把握すると共に,今後指導が必要とされる事項について確認し今後の指導の参考にするため,以下の設問を設けた。昨年度からは昨今の社会情勢を踏まえ,インターネットの掲示板に関する項目を追加している。 |
|
| 質問17.自分の他に友だちも写っている写真をホームページに出す時,気をつけなければならないことは何でしょうか。 |
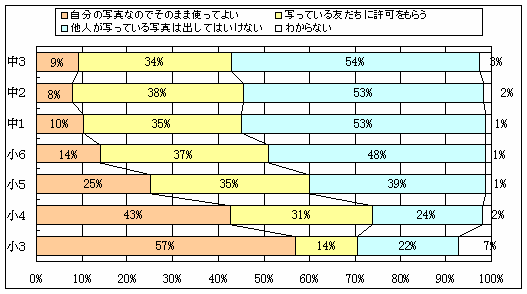 |
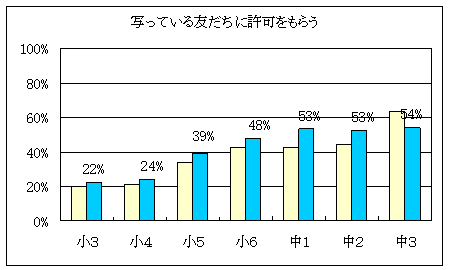  2005年度 2005年度  2006年度 2006年度 |
|
|
| 質問18.他人のホームページにのっている詩や写真を自分のホームページに載せる時,気をつけなければならないことは何でしょう。 |
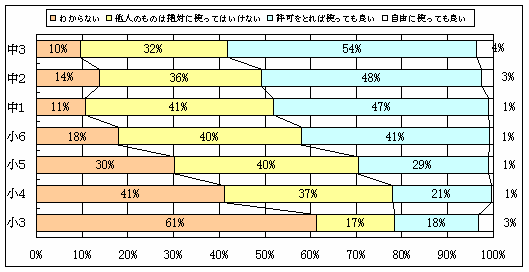 |
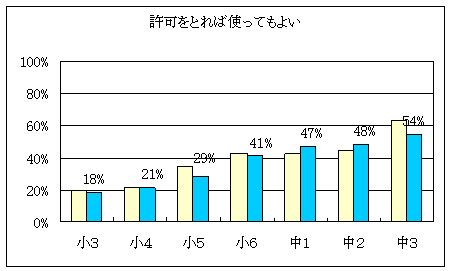  2005年度 2005年度  2006年度 2006年度 |
|
|
| 質問19.インターネットで調べているうちに,変な写真が掲載されているページが現れました。あなたはどうしますか。 |
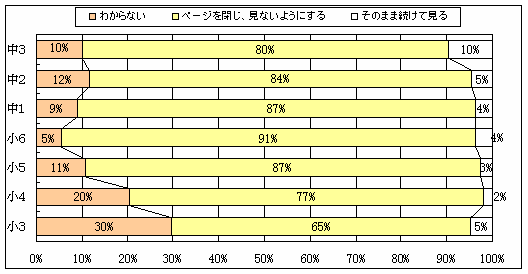 |
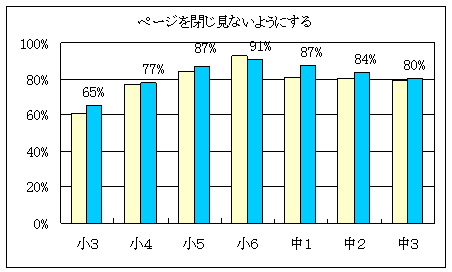  2005年度 2005年度  2006年度 2006年度 |
|
|
| 質問20.家に「24時間以内に,5人この電子メールを出さないと,あなたは不幸になる。このメールをすぐに出しなさい。」というメールが届きました。あなたはどうしますか。 |
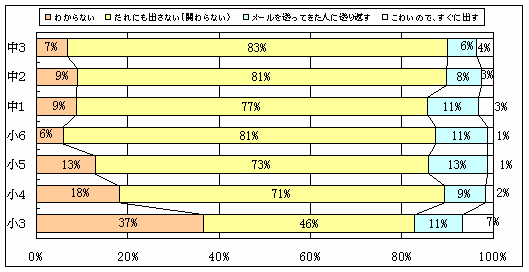 |
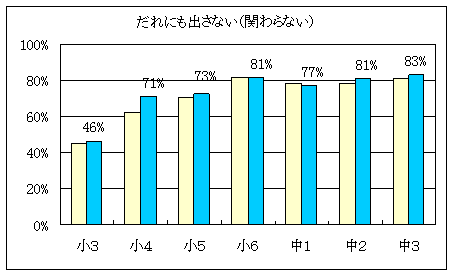  2005年度 2005年度  2006年度 2006年度 |
|
|
| 質問21.インターネット上で知り合った人に,伝えて良いあなたの情報はどれでしょうか。すべて選んでください。(複数回答可) |
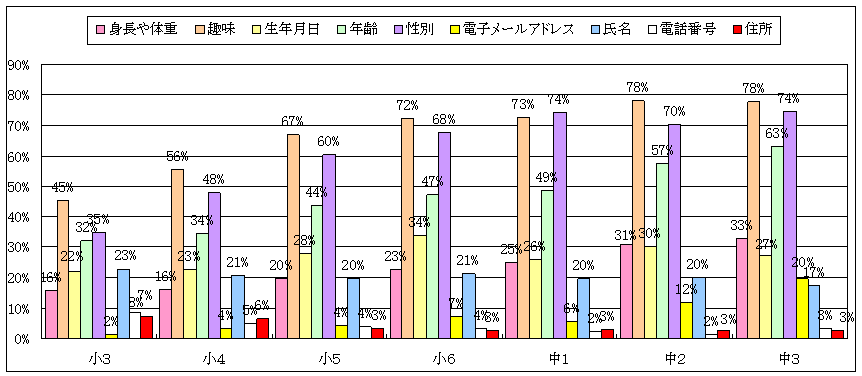 |
|
| 質問22.学校でインターネットを見ている時に,学習に役立ちそうなプログラムソフトを見つけました。あなたはどうしますか。 |
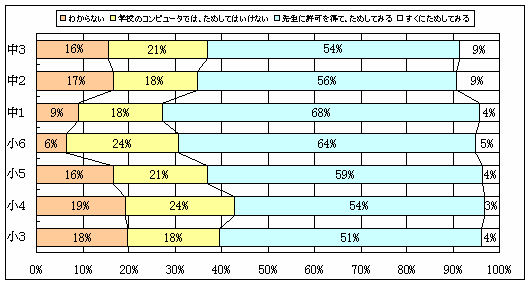 |
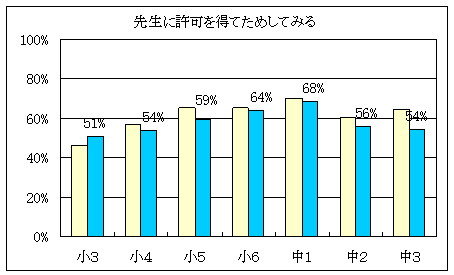  2005年度 2005年度  2006年度 2006年度 |
|
|
| 質問23.学校でインターネットをしているうちに,急にうずまき模様が画面に表れるようになりました。あたなはどうしますか。 |
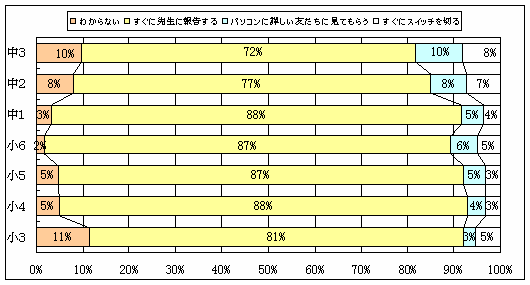 |
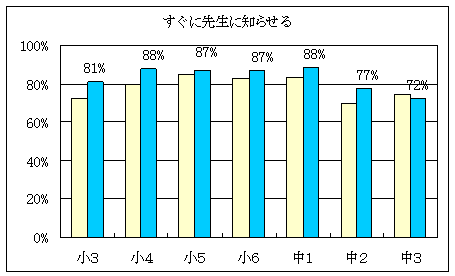  2005年度 2005年度  2006年度 2006年度 |
|
|
| 質問24.コンピュータのパスワードを管理するためには,どうすればよいでしょうか。 |
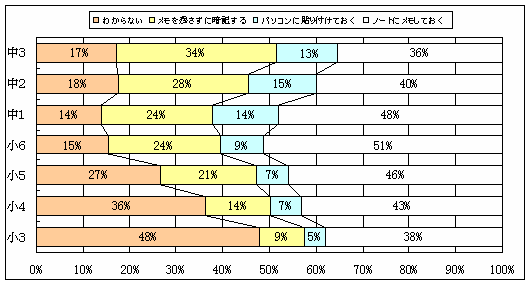 |
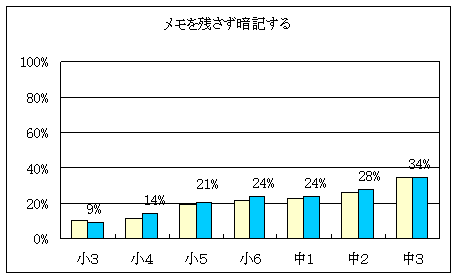  2005年度 2005年度  2006年度 2006年度 |
|
|
| 質問25.インターネットで買い物をする時に大切なことはなんでしょうか。 |
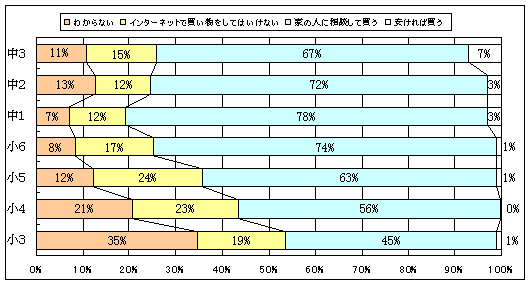 |
|
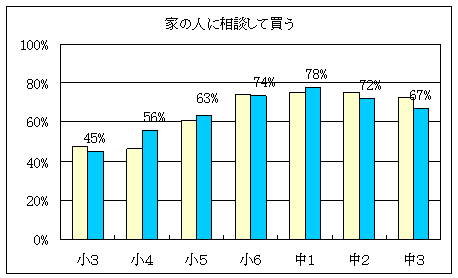  2005年度 2005年度  2006年度 2006年度
|
|
|
| 質問26.インターネットの掲示板に,自分の自慢話を書いたら,そのことについて悪口を書かれてしまいました。あなたはどうしますか? |
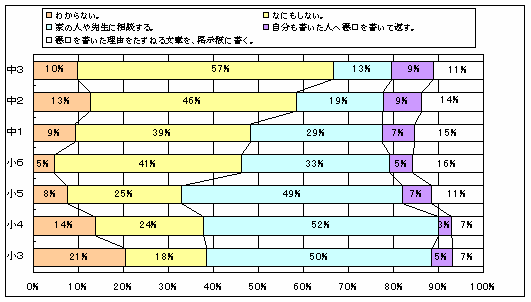 |
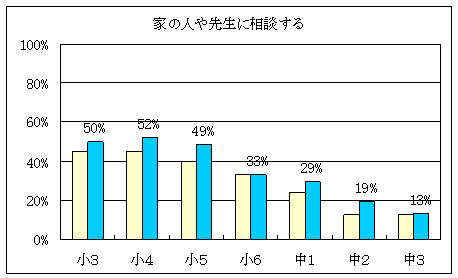  2005年度 2005年度  2006年度 2006年度 |
|
|
| 【 考 察 】 |
|
著作権や個人情報保護,有害情報やネット上のトラブルに対する対処の仕方などについての児童生徒の認識は,わずかではあるが高まってきている。この分野は,学校での指導が結果に大きく影響してくると思われる。学年ごとのグラフを比較してみると,小学4年生〜中学1年生あたりの時期に適切な指導が行われるようになってきたと読み取ることができる。特に,小学校高学年の時期の指導が効果的だと言えそうである。
昨年度の考察でも,年々身近になるネットワーク社会に対応できる力を育成するために「情報モラル教育」を推進していくことの重要性が述べられた。今後も,学校全体の取り組みとしてとらえ,計画的に指導していくことが必要である。
情報モラル教育については,指導の参考になるWeb上の資料や教材が,学習センターポータルサイトのリンクページでも紹介されている。また,各校の主体的な取り組みを補助する形で,学校支援事業のサポートも受けることができる。リテラシーの部分でもふれたが,共有キャビネット等を利用して他校の取り組みを参考にし,情報を交換しながらよりよい指導法を追究していくことも可能である。
情報モラルについては,関係機関や専門家との連携を図りながら指導を進めている学校や,家庭への啓蒙等も視野に入れながら取り組んでいる学校がある。子どもの実態と情報化に伴う諸課題について,学校と家庭間で認識を共有していくこと,子どもの状況や発達に合わせて指導内容を見直しながら,子どもが安全にITを利用することができる環境づくりを進めていくことが,今後ますます重要になってくる。
|
|
|
|